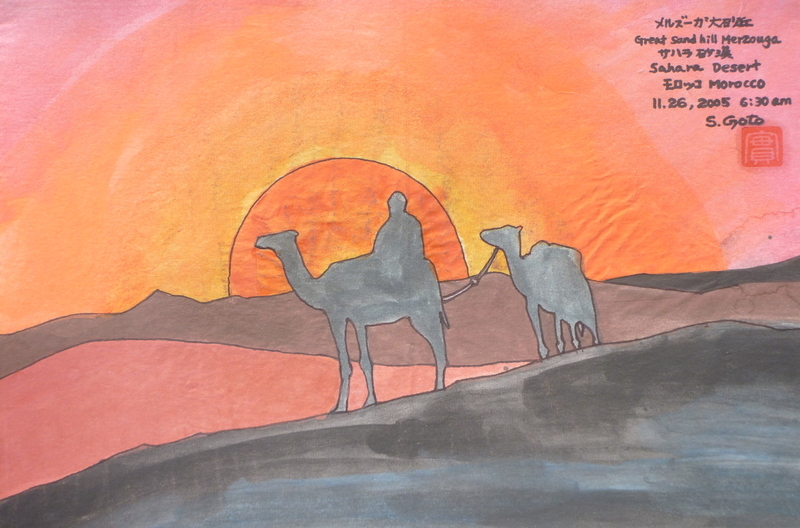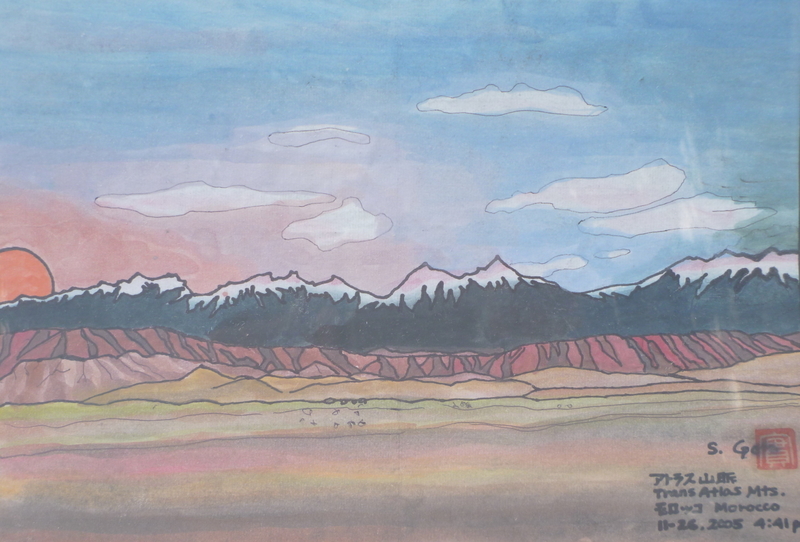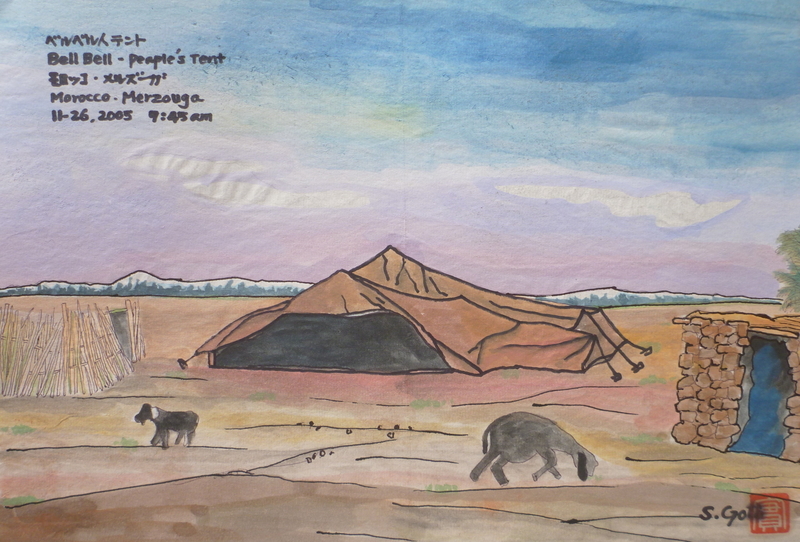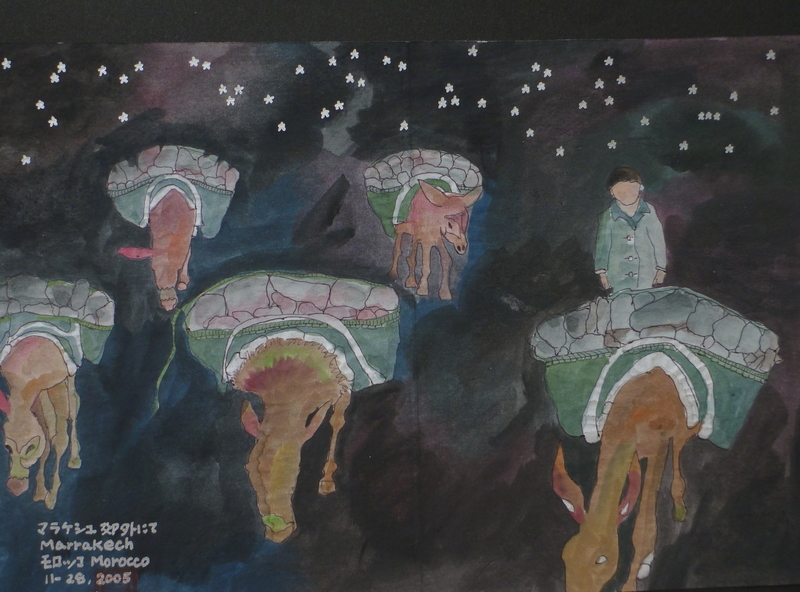『星の巡礼 ヨーロッパ周遊の旅 11000km』
Ⅰ ヨーロッパ前半 《スカンジナビア半島・イギリス・アイルランド 5500kmの旅》
2022年3月、ロシアによるウクライナへの特別軍事作戦が開始され、世界の目がロシア
大統領の前近代的な歴史観<大ロシア帝国>により、<国土回復、いや一度ロシア領で
あった地域は、ロシアの地に還る>というロシア正教独特な考えを見せられることとな
った。
さっそく、本棚に眠っていた旅日記を取りだして、約20年前のソビエット連邦から
解放されて間もない2001年当時のロシアを覗いてみたくなったのでシベリア横断鉄道に
飛乗った。
その後、ヨーロッパ周遊の旅に向かうはずであったが、2023年10月に、ガザを実効支
配する武装勢力ハマスによって、イスラエルへの越境攻撃による大量殺戮と、約260名
にのぼる人質を拉致する事件が起き、急遽 『イスラエル縦断の旅 1100km』 を
取り上げることとなって、横道にそれていた。
ようやく、ユーラシア・アフリカ二大陸 38000km の旅にもどり、ここではヨーロッパ
前半としてスカンジナビア半島を縦断し、イギリスからアイルランドへ向かうことにする。
ただ、2024年現在、ここスカンジナビア半島も、ロシアと接するフィンランドや、バル
ト海でロシアと接しているスエーデンも、ロシアのウクライナ侵攻をみて、中立政策を
捨て、NATOという相互安全保障条約の傘のもとに加入することとなり、2001年当時の
スカンジナビア半島は、中立地帯として貴重な存在であった。
では、バックパッカーの見た2001年当時の、平和なスカンジナビア半島から、イギリス
そしてアイルランドの旅へ、ご一緒しましょう。
■ 《スカンジナビア半島縦断 5000km 南下の旅》
では、《ヨーロッパ周遊の旅 11000km》 の入口、フインランドの首都ヘルシンキに向
かうことにする。
2001年9月20日、ロシア・サンクトペテルブルクを国際列車(アレグロ直通列車・距離
443km・所要3.5h)で出発し、フィンランド首都ヘルシンキへ向かった。

ヘルシンキ行国際列車<ALLEGRO>

《ユーラシア・アフリカ2大陸の旅 38000㎞》 全ルート図

<スカンジナビア半島縦断列車の旅 5000km> ルート図
朝2時に起床、シベリア横断時の収集品や、旅日記を追記し、携行品を再点検、不用品
を選び出し、バックパッカーのモットーである<コンパクトこそ最高>に従ってフィン
ランド行パッキングを行う。
処分する品は、ホテルの部屋係であるおばちゃんにプレゼントすることにした。
テレビのCNNチャンネルは、9:11同時多発テロ事件のニュースを流し続けている。
世界貿易センターであるツインタワーでの死傷者や不明者を含めると、約5000名(後日
の報道で、最終的に死者2749名)に達するという。
悲惨なテロ事件に対し、アメリカの出方が注目される。
<時の流れが止ったシベリア、広大なロシアからの脱出>
ピロシキとオレンジジュースで簡単に朝食を済ませ、ロシア最後の地 サンクトペテルブ
ルグのソビツカヤ・ホテルを 05:00 にチェックアウト、フインランド駅(サンクト
ペテルブルグのヘルシンキ行発着駅)に向かう。
風邪っ気で頭がぼやけていたのか、シベリア時間にボケていたのか、昨日下見しておい
たフィンランド駅への道順を間違えて右往左往してしまった。 どうも、地下鉄の下車駅
を数え間違えたようである。
ヘルシンキ行の列車の発車時間が迫るなか、ぼやけた頭がますます混乱する。
とっさに街路に出て、タクシーに乗り、運ちゃんに事情を説明すると、「お客さんは、
間違った駅に降りたんだね」と事情を察し、夜明けのサンクトペテルブルグの街をぶっ
飛ばしてくれた。
広大なロシアの大地で、タクシーを飛ばすおのれの姿が滑稽に見えたものである。
シベリアと言う優雅に流れる時間に身を任せていたはずなのに、ロシアを離れる途端
に、また時間に縛られた都会人にもどされたのだから、文明は恐るべき機械的な人間を
作り上げているのだと、思い知らされたものである。
<ヘルシンキ行国際列車> 「赤い矢号」 Красная стрела
サンペテルブルグ05:53発➡12:17ヘルシンキ着
Train#33 4号車 コンパートメント3(定員6人用)
男女カップルとの3人の同室

<ヘルシンキ行国際列車>ALLEGRO「赤い矢号」
ヘルシンキ行の国際夜行特急列車<赤い矢 ALLEGRO>に乗車すると、車掌にチケット
と、命より大切なパスポートと添付された出国証明書(ビザ)を回収されてしまった。
いくらパスポート、ビザのコピーを持っているとはいえ、これじゃ、まるで身分を剥
奪された囚人と変わらないではないか。
それにここはまだロシアであるという緊張感と、丸裸であることに一抹の不安を覚
えたが、コンパートメント同室のロシア人男女は平然としているのを見て、郷に入れば
郷に従えの例え通りに気を鎮めたものである。
乗客へのクッキーとヨーグルト、りんごジュースが配られ、列車がゆっくりとヘルシン
キ駅を後にしたときは、不安も消え去り、ようやく落ち着きだした。
これから、広大なユーラシア大陸の3分の2を占めるロシアから、その西に広がる
ヨーロッパへ向かうのである。 それも、この星で一番早くから文明という言葉が定着し、
近代化が推し進められてきた欧州に向かっている。
フインランドは、北欧の一角にあり、ロシアとも1340㎞の国境を接している陸続きの国
である。
歴史的にも、フィンランドはロシアに盗られたり、奪い返したりと、大熊に立ち向かう
森の小人のような関係にある。
小国が隣国である大国に立ち向かうことの困難さを歴史的に学んできた国であり、国民
である。
生存する知恵は素晴らしく、独立国としてロシアに認めさせているのだから、日本も学
ぶべきところが多々あり、興味深い国である。
これから、かかる民族的悲哀を歴史的に味わって来た国に入るのだ。
美しい白樺・ピリョーザの国境が続く。 車掌が<出国申請書>を配りに来た、国境が近
いようである。
現在、列車が通過しているロシア・フィンランドの国境付近は、フランスのナポレオン
軍やドイツのヒットラー軍が、レニーングラードを攻撃した折、冬将軍に戦い敗れた原
野である。

冬将軍に敗れ撤退するナポレオン軍

冬将軍に敗れ捕虜となったドイツ軍将兵
<ロシア国境の村 Vyborg / ヴィープリ>
ロシア側国境の街<Vyborg/ヴィープリ>では、婦人係官が乗込んできて、「出国カー
ド」・「税申告カード」をチェックし、荷物の個数と中身をチェックするという簡単な
検査に安堵したものである。
なぜなら、これが1991年以前のソ連赤軍による検査であるならば、厳しいチェック、身
体検査、尋問などがなされていただろと想像してみたからである。
車窓からは、ロシアの貧しいスレートのブリキ屋根、それも温かさの消えた灰色一色で
ある。 厳しい冬将軍をどのようにしのいでいるのだろうか・・・凍える農民の姿が脳
裏に浮かんだ。
ロシア国境の村<Vyborg/ヴィープリ>駅で約20分間停車したあと、列車が動き出して
から、乗込んできた国境警備隊による徹底した検査が始まった。
まず、無言でにらみつけるような威嚇の目で、顔とパスポートを確認、その後、名前を
読み上げてまたじろりと一瞥、コンパートメントから乗客3名を外に出し、室内のチェ
ックが行われた。
土足で寝台の階段を上り、天井の隙間やベットの下までめくりあげてのチェックがくま
なく行われた。
多分、麻薬・偽札・銃器・ポルノ・機密情報(パテント・地図・写真)等の持出し、又
は持込の捜索なのであろう。
写真機と双眼鏡をベットに出していたのでびくり、どっきり、生きた心地がしなかった
ものである。 ロシア・シベリアでの恐怖を想いだし、フィルムを抜き取らりたり、双
眼鏡を没収されたりしないかと恐れたものである。
今でも不明なままだが、この国境警備隊がロシア側なのか、フィンランド側なのか分か
っていないのであるから、当時の恐怖が分かるというものだ。
僅かフィンランド国境の村までの十数分間の出来事であった。
今から振返ってみると、同室者の男女のカップルに何らかの容疑、嫌疑または、密告が
あったのではないだろうかと思ったほどである。
それとも、東洋人であるバックパッカーに対して、ロシアを離れるにあたっての最後の身
辺チェックがなされたのであろうか・・・、 ともなれば私はロシア横断中見張られてい
たことになるのである。
この時期2001年、ロシアはいまだソビエット共産体制の崩壊から10年目の、国家主義
体制から民主主義への移行の混乱時期であり、古い秘密警察の機能が引き継がれていた
とするば、私の妄想だけではなさそうである。
<フィンランド国境の村 Vainikkala / ヴァイニッカラ>
09:50am フィンランドに入り、国境の村<ヴァイニッカラ>駅に着いた。
シベリア横断は、ロシアと言う、いまだ冷たい官僚主義的な国家風土の抜けきらない、
コルホーズ的社会のなかに生きながらも、素朴な本来の親しみあるロシア民衆の温かさを
感じたものである。
この瞬間、ロシアという国家権力と、人間本来の純粋なロシア人のギャップに戸惑いな
がらも、民主主義国家であるフィンランドとい童話の国に入ったのである。
そう、スカンジナビア半島というバイキングのテリトリーに入ったのである。
なにか、急に緊張がほぐれ、すこし疲れを感じた。やはりロシア横断中は緊張の連続で
あったのであろう。

フィンランド国境の村 Vainikkalaヴァイニッカラ駅

フィンランド国旗
<バイキング>
「バイキング」と口にするとき、すなわち中世のスカンジナビアのバイキングがただ略
奪を繰り返した野蛮な海賊のようにイメージしがちである。
スカンジナビアに住んでいたバイキングが、襲撃や略奪を行ったのは確かである。
しかし一方、彼らは遠くまで旅をし、北大西洋、スコットランド諸島の一部にも入植
し、アイスランドや、シベリアの川や水路へも進出していた。
グリーンランドに500年にわたる植民地を作り、北米の端にまで進出していたことはあ
まり知られていない。
アメリカは、コロンブスによって発見されたというより、バイキングによって第一歩が
記されたと言ってもいいのではないかと言う説があるほどである。
バイキングは、探検家であり、冒険家でもあったのである。

バイキングのイラスト
フィンランド国境の村<Vainikkala/ヴァイニッカラ>駅からフィンランドの管理官
(兵士)が乗車してきた。
自動機関銃を肩にかけた、おっかない軍服姿の兵士がパスポートチェックをしながら、
日本語で「こんにちは!」、「どうもありがとう!」と笑顔でご挨拶、これが解放され
た自由の国なのかと、緊張から解放されていく自分に気づいた。
「フィンランドには、どれくらい滞在し、いつ頃お国へ帰られるのですか」、もちろん
英語である。
「お国には、3日間滞在し、クリスマス頃帰国する予定です」・・・なんと平和な国境
通過であろうか。
広大なロシアと違って、田畑もきちんと手入れされ、アスファルト道がきれいに整備さ
れている。
白樺・モミの木、松、杉の木立が無数の湖やの池に投影し、美しい北欧の景色が迎えて
くれた。
<北欧の男女平等>
ロシア女性のセックスアピールは、本人たちが充分承知、意識した上で男性にアッピー
ルしているようである。
恐らく、ブラジルの情熱的な女性に負けないほどにロシアの女性、とくに独身女性は、
世界で一番魅力を発散させているのではないだろうか。
それに対して、ロシアからフィンランドに入ってまず驚いたのは、男女の違いがなく、
そこにはセックスアピールなる物の存在が無く、男女同権たる、高貴なる大人の姿とし
て目に映ったものである。
かえって、凡人たるわたしには、もうすこし女性らしい表現の在り方を追求してもらっ
た方が、世間全体として幸せを感じるのではないかという思いにさせられたほどであ
る。
北欧では、すでに男女平等が達成され、次の段階へと向かっているようだ。
かえって、日本の男女の格差、あり方に後進性を見た思いで愕然とさせられたと言って
いい。
日本も成熟社会に入り、人口減少が問題視されてきた。
フィンランドはじめ、北欧の男女平等による国家維持の手本を、受け入れる時期に差し
掛かっているように思えたのである。
<水の都 ヘルシンキとサンクトペテルブルク>
12:17 定刻にヘルシンキ駅に列車は滑り込んだ。
サンクトペテルブルクは水路で結ばれた水の都であり、一方、ヘルシンキは多くの島で
成り立つ<水の都>と言っていい。
古い歴史の中で洗練されてきた両都市とも、水路をつなぐ船・島を結ぶ船の多さに<水
の都>の情緒をよく醸し出しているのである。
ヘルシンキでは、海外からの観光客にあふれ、それもクルーズを楽しみながら北欧の短
い日光浴に体を横たえる老夫婦を多く見かけた。
また、ヘルシンキには世界中の若いバックパッカーが集まっているのではないかと目を
疑うほどのバックパッカー天国である。
ヘルシンキ中央駅近くの屋外マーケット「Kauppatori(カウパットリ)」や、空飛ぶサウナ
(ゴンドラ)も人気があるようだ。
みな思い思いのバックパック・スタイルで、ここ<バルト海の乙女>ヘルシンキで、ム
ーミンやサンタクロースの物語に浸っているようである。

ヘルシンキ駅に到着

水の都<ヘルシンキ>の交通手段フェリー
ヘルシンキに数泊したかったが、ユーラシア・アフリカ大陸踏破の途上の事、残念なが
ら今夜の夜行列車で、次に向かうことにした。 というよりも都会のYH(ユースホステ
ル)よりも、田舎の静かなYHに泊まりかったのである。
まずは、腹ごしらえである。 栄養補給のため日本レストラン<古都>か、中華料理
<ロータス>で迷ったが、やはり持ち帰りのできるバックパッカーの常食である中華を
選んだ。
何といっても、中華はボリュームがあり、その半分を箱詰めにしてもらい移動中の携帯
食にできる優れものなのだ。


ヘルシンキ市街散策

ヘルシンキ大聖堂
<フィンランド と ロシアとの歴史的関係>
ロシアとフィンランドの歴史的な関係は、数世紀にわたり様々な要因によって形成される。
以下に、主な時期や出来事を中心に歴史的な経緯を見ておきたい。
➀スウェーデン時代 (12世紀初頭 - 1809年):
フィンランドは長らくスウェーデンの一部であった。スウェーデン時代中、フィンランド
はスウェーデン王国の一部として統治され、スウェーデン文化や統治機構の影響を受け
た。この時期、フィンランドの都市や文化が発展した。
②ロシア帝国時代 (1809年 - 1917年):
ナポレオン戦争の影響で、スウェーデンはロシアに敗れ、1809年に結ばれたトルン条約に
よってフィンランドはロシア帝国の一部となった。しかし、帝国内で特殊な地位を保ち、
自治権を維持した。この時期、フィンランドはロシアの文化的・政治的影響を受けつつも、
相対的な自治を享受していた。
➂フィンランド独立 (1917年):
ロシア革命の影響を受け、1917年にフィンランドはロシア帝国から独立を宣言した。
この出来事はロシア帝国の混乱期に起こり、フィンランドが独立する際には比較的平和的な
形で行われた。
④冷戦時代 (1944年 - 1991年):
第二次世界大戦中、フィンランドは継続戦争(独ソ戦におけるフィンランドの一環)で
ソ連と戦ったが、戦後にモスクワ講和条約を締結し、ソ連との平和を確保した。
冷戦時代、フィンランドは中立政策を採り、ソ連との隣国関係を維持しつつ、西側とも
経済的なつながりを築いた。
⑤冷戦後 (1991年以降):
冷戦が終結すると、フィンランドとロシアの関係も変化していった。
フィンランドはEUやNATOに加盟せず、中立を維持しつつも、両国は経済的な協力や
文化的な交流を進めている。
国境問題や安全保障上の懸念が存在するものの、一般的には平和的な関係が続いていた。
⑥最近(2024年~):
2023年のロシアによるウクライナ軍事侵攻を受けて、フィンランドとスエーデンは
安全保障上、中立政策を破棄し、NATO加盟を申請し、受理された。
スカンジナビアである北欧3国はノルウエ―を加え、NATO加盟国となり、ロシアに対峙する
ことになった。
▼ 10/20 夜行列車 <ヘルシンキ➡ケミ/KEMI> 列車泊
《夜行特急列車 #P-69便》
ヘルシンキ10/20 22:28発➡(列車)➡ KEMI・ケミ 10/21 09:15着➡(連絡バス・国境越え)➡
スエーデン国境の街<Haparanda・ハパランダ>➡(連絡バス)➡ Lurea/ルーレア駅

《夜行特急列車 #P-69便》
《ノルウエ―最北鉄道オーフォート線 列車#ST-4便》
スエーデン・Lurea/ルーレア駅発➡<最北鉄道オーフォート線>➡ノルウエ―・Narvik/ナルビク

ノルウエ―最北鉄道オーフォート線を走る
貨物列車#123

■ 9月21日 <フィンランドからノルウエ―に入る> 天候・晴れ 気温8℃
夜行特急列車 #P-69便は、快適に北に向かっている。
コンパートメントの中段(3段ベット)、ゆったりしたスペースに朝の光が差し込んで
きた。
昨夜、列車に乗込んでから旧ソビエット時代の専制的な官僚制の残っていたロシアから
の離脱に気がゆるんだのだろうか、自由世界の神話<安心安全>の中に吸い込まれて、
無防備にぐっすりと熟睡してしまっていた。
朝6時に起床してから、北欧の洗練された特急列車の設備やもてなし(ミネラルウオー
ター・タオル・石鹸・飴ほか)に感心しながら洗面を終え、食堂車に向かった。
コーヒーを飲みながら、車窓から見る北欧の大自然、そこに隠されている生命の神秘、
大宇宙の営みに触れ、生きる力がみなぎってきたものである。
スカンジナビア半島の付け根、ボスニア湾に面するオウル(Oulu)で迎えたフインラン
ドの夜明けの風景<湖・森・夜明け・白樺・パインツリー>をスケッチに収めながら、
スカンジナビア半島の列車の旅をエンジョイした。

フィンランドの夜明け
Oulu近郊 列車の車窓から
Sketched by Sanehisa Goto

食堂車でスケッチ中 (特急列車 #P-69便/ヘルシンキ➡ケミ)

洗練された特急列車を背に(オウル駅で)
<ノルウエ―最北鉄道路線・オーフォート線乗車>
オウル駅を過ぎると、スエーデン国境に近いKemi・ケミ駅に到着する。
ここからノルウエ―の北極圏にある<Narvik・ナルビク>に向かうが・・・少し煩雑なので、
少し経路について説明しておきたい。
まず、ケミからスエーデン国境の街<Haparanda/ハパランダ>へ連絡バスで移動する。
ここから10:30発バスで、最北鉄道路線<オーフォート線>に乗るため、始発駅Lurea/ルーレア駅に
バスで向かう。
この間、鉄道路線がないためバス移動となる。 ただバックパッカーとして助かるのは、バス代が
ユーレイル・パスに含まれていることである。
また、ノルウエー最北鉄道路線の列車に乗れるという夢がかなうので、何一つ苦にな
らないのである。

スエーデン国境の街 Haparanda / ハパランダのバスステーション
ここから連絡バスで Lurea/ルーレア鉄道駅へ向かう
Sketched by Sanehisa Goto
ハパランダから、ノルウエー最北鉄道路線<オーフォート線>の始発駅とも言える
Lurea/ ルーレアまでは、約2時間のバスによる車窓観光である。
スカンジナビアの国々は、GDPが高く世界で一番豊かな国々である。
美しい白樺の林を見ながら高速道路が南に向かっている。
野生動物の保護、危険な横断を防ぐために、延々と網のフェンスが続く。
12:30 時間通りにバスは、ルーレアのバス・ステーションに滑り込んだ。
次のナルビック行列車<TRAIN#ST-4>は、3時間後に出発するという。
すこし気分転換にルーレアの街を散策することにした。
ノルウエ―最北鉄道路線、北極圏を走る路線の始発駅と言うことであろうか、
この小さな町に、世界中のバックパッカーが集まったような観がするほど賑わって
いた。

ルーレオ大聖堂 (ノルウエー)

ノルウエ―国旗

<ノルウエ―最北の鉄道路線 オーフォート線> 1903年開通、 全長42km
スエーデン / ルーレア駅
⇑
➡(国境まで363km) スエーデン側 / MALMBANAN線 / マルム線
⇓
( ノルウエ―国境)
⇑
➡(国境から42km) ノルウエー側 / OFOTBANEN線 / オーフォート線
⇓
ノルウエー/ナルビク駅

<ノルウエ―最北の鉄道路線 オーフォート線>路線図
ノルウエー/OFOTBANEN ⇦(国境)➡スエーデン/MALMBANAN線/マルム線

ノルウエ―最北の鉄道路線<オーフォート線>
<ルーレオ➡ナルビク>間を走る列車 #ST-4
Sketched by Sanehisa Goto
たくさんのバックパッカーや観光客の夢を載せたノルウエ―最北路線を突っ走る列車#ST-4は、
まるで銀河鉄道999のように<Arctic Circle / 北極圏>を通過した瞬間、車掌のアナウンス
に、みな歓声を上げたものである。
―いま、わたしはここにいる。 そう、北極圏にいるのだー
北極圏の夕陽がきれいだ、松林の木陰をぬって真っ赤な大きな顔が駆け足で、過ぎ去っ
ていく。
《白樺の 木洩れ日舞いし 北極圏》 實久
想像していた極寒はどこへやら、外気は10℃、ヘルシンキで購入したマフラーの出番は
あるのだろうか。
夕食は、バックパッカー食<ピロシキ大2個・オレンジ・チョコ>で済ます。
終点ナルビックには真夜中に到着するので、もしものことを考え非常食としてビスケッ
トは残すことにした。
予定では、Kiruna/キルナで泊まる予定であったが、終点のNarvik/ナルビックまで行っ
て、ゲストハウスを探すことにした。 それにしても、なぜか乗客のほとんどがキルナで下車し
てしまったではないか。
後で分かったが、北極圏であるこの辺りの宿や店は、夜8時頃には閉店してしまうと言
うことだ。
ましてや到着予定の 21:00 では、旅行者は路頭に迷うことになると言うことであ
り、まさにその受難者となったのである。
最果ての街ナルビック駅に着いた時、車両に一人取り残され唖然としてしまった。
この北極圏の最果ての街に、まだ少し明かりが残る駅に、数名の旅行者の一人として降
り立ったのである。
侘しさを通り越して、映画の一シーンのような死の町に放り出された。

北極圏の明るさ残る街ナルビクに到着
<北極圏で野宿をする>
いくら体力があると言っても北極圏の9月下旬、夜中の最低気温である0℃を、野宿で
過ごせるか心配である。
▼9/21 野宿 ナルビック(北極圏) ノルウエ―


ノルウエ―最北の鉄道路線図<オーフォート線>ルーレオ➡ナルビク
■ 9月22日 Narvik/ナルビク ノルウエ―
実は、前もってナルビクでの宿泊先としてゲストハウスの所在を確かめていた。
人一人出会わない真夜中の街を歩いて、かすかな望みをもってシティホール近くにある
ゲストハウスに向かった。
ゲストハウスはすぐに見つかったが、灯りは消え、ブザーを押せども応答がない。
真夜中の事、不審者として招き入れられるはずもなく、観念し、朝になれば温かいコー
ヒーでも飲ませてもらえたらと、玄関先での野宿で一夜を明かすことに覚悟を決めたの
である。
北極圏にあるナルビクは、白夜がまだ完全に終わっていないのか、明るさがまだ少し残
っているだけに恐怖は感じることはなかった。
かえって、人の住むゲストハウスの玄関先、いや軒先であるというだけで、厳しい寒さ
であったが安心して眠りにつけたものである。

ゲストハウス玄関先での野宿スタイル
北極圏での野宿スタイルを記録したスケッチが残っているので紹介しておきたい。

北極圏での野宿スタイル
寒さのため3時間程の仮眠のあと、朝ゲストハウスの玄関の戸を再度ノックしてみた
が、応答がない。 やはり予約客が無く、閉じていたようで、オーナーもゲストハウスを離
れていたようであることが分かった。
北極圏の星を眺めながら、凍てつく夜空のもとで野宿が出来るなどバックパッカー冥利
に尽きるものである。 何といっても<北極圏>というロマンを含んだ響きがいい、夏
だったら白夜を経験できていただろうと思うと、ちょっぴり残念である。
寒いはずである、昨夜ナルビクに夜遅く着いて分からなかったが、周囲の山は雪におお
われていた。
しかし、冷えた体を温めるための温かいコーヒーどころではなくなってしまった。
出立の準備をして、北極圏での野宿と言う貴重な体験に感謝し、ゲストハウスの玄関先を離れ、
<ナルビク・バスステーション>に向かった。
では、北欧ノルウエ―のフィヨルド、いやバイキングの巣窟のあった入江を、フェリーに
乗ったバスから眺めながらの旅行に出かけることにしたい。
バスには、アメリカ人2名・ドイツ人2名・ノルウエ―人2名に日本人の計7名、もちろん
全員バックパッカーである。 すぐに意気投合、情報交換に話が弾んだ。
<バス+フェリー旅行>
Narvik/ナルビク(バス+フェリー)➡Bode/ボーデ経由(これより列車)
➡Trondheim/トロンヘイム行
ナルビク 07:30 発 長距離バスに乗り、ナルビクの港からフェリーにバスごと乗船し、
ファウスケ近郊のボーデ港で下船し、列車に乗り換えてトロンヘイムへ向かう。
ノルウエ―の西海岸は、切り立った崖を持つフィヨルドの入り組んだ国道なので、
途中道がなくなり、フェリーが国道に早変わりし、バスと乗客を乗せて北極圏の船旅を
楽しませてくれるのである。
終点トロンヘイムまで、約900㎞、14時間の、北極圏のフィヨルド風情を眺めながらの
長距離バス+フェリー+列車というロマンに満ちた旅である。
フェリーが出航して間もなく、北極圏にあるロフォーテン諸島の山々が、神秘的にそび
えているではないか、さっそくスケッチブックに絵筆を走らせた。

北極圏にあるロフォーテン諸島を望む on Ferry<TYSFTORN>
Sketched by Sanehisa Goto
フェリーから眺めるフィヨルドの景色は絶景である。 人を寄せ付けない厳しい岩場
や、背景の雪を頂いた、神の宿る不思議なほど寒々とした雪渓を持つ山容は、エスチュ
アリー(三角江)というあまり土砂が運び込まれない入江を創り、奥に大小のフィヨル
ドを隠し持つというノルウエ―の海岸でしか味わえない光景である。
ここに、バイキングが隠れ、船を襲ったのかと思うだけで、あの荒々しい海賊風の戦士
を少年時代に愛読した雑誌<少年>や<冒険王>で見たことを思いだしたのである。

バイキングのイラスト
- KING HAAKON-
冬の旅、それも地球最北の北極圏の旅もいいものだ。
遠くの山岳の峰々にかぶさる純白の雪渓の輝きに吸い付けられ、
フィヨルドの入り江に映り、揺れ動く黄葉の縞模様の美しい風情に見惚れ、
白樺林に音を立てて、幾筋もの細い急流が走り、
天どこまでも青く澄み切り、今にも雪が降りそうな冷たさに頬が赤く染まりゆく、
水鳥だろうか、この一枚の油絵の額縁の中を、悠々と飛翔している・・・・・
この瞬間、すべて神のなせる業、美しいと言おうか、厳しいと言おうか、人智を越えた
表現が見つかりそうにもない。
ただただおのれを風景に溶け込ませ、率直に美しさを味わった。
いつかは、この死を迎え入れてくれる大地のこの美しさに、いかに対処すべきか、この
わたしと言う汚れた肉体が気にかかるのである。

スカンジナビア山脈をフェリーから望む
(フェリー下船港ファウスケ手前の入江から)
フェリー船長から、終着ファウスケ近郊ボーデ港に近づいた時、この先に目には見えな
い北極圏線(北緯66度33分)があるとのアナウンスがあり、乗船客は遠くに横たわる雪
を抱くスカンジナビア山脈に向かって<ブラボー>を叫んだものである。
この旅での2度の北極圏通過は、幻のアトランティック大陸探索にも劣らない興奮を
味わせてくれた。 若い時、船で通過した赤道を懐かしく思い出していた。
ノルウエーのフィヨルド海岸とそれを創り出している山々と言うのは、一枚の岩の塊で
できているようだ。 それも古代から、人類がこの世に姿を現わす何万年もの前から、
時間をかけていまの姿を創って来たと思えば、自然の偉大さに驚嘆させられるのである。
<スケジュール変更>
ナルビクを出て、約5時間で<バス+フェリー>は、250km 先のボーデ港(ファウスケ
近郊)に着岸した。
目的地であるトロンヘイムまでは、ボーデ港よりファウスケ経由897㎞もある。
昨夜の睡眠不足を取り戻すため、港にある<ボーデ・ユースホステル>に急遽泊まるこ
とにした。
睡眠不足では、フィヨルド探検の醍醐味も半減してしまうので、思い切って予定を変更
したのである。
YHは、ボーデ港バスターミナル・ビルの2階にあり、便利だったことと、近くに中華料
理店があり、毎日バックパッカー食である携帯食ばかりで、美味しく栄養のあるものを
摂る必要があったことが予定変更を決心させたのである。
ボーデ港のチャイニーズレストランは、「竹龍」という。
肉と野菜たっぷりのローメン、シュリンプ・カクテル、ワンタン・スープに、ライス付と、
豪華に注文した。
もちろんノルウエーのクラフトビール<OSLO>で乾杯。 コーヒーで締めくくった。

フェリーは<ボーデ港>に着いた
Ferry<TYSFTORN>

ボーデ港で出会ったハーレ仲間と
ノルウエー性風俗二景、素っ裸でシャワルームより出てきて前を隠さず立ちはだかる若
い女、トイレでこちらの一物をじっと眺め、ぶつぶつ言っている中年男、東洋の美青年
にモーションをかけているのだろうか・・・・(笑い)
▼ 9/22 宿泊 <BODO VANDERHJEM Youth Hostel> (ボーデ/ノルウエー)

BODO VANDERHJEM Youth Hostel

ボーデ・ユースホステルのドミトリーで
■ 9月23日 列車移動 <ボーデ駅➡ファウスケ経由➡トロンヘイム>
静かな日曜の朝、午前中は海を眺め、フィヨルド迫る街を散策し、ヘルシンキ以来の過
密スケジュールからくる疲れをとることにしている。
ボーデの街を散策し、句を作りスケッチをしながら過ごすことにした。
ボーデは、ちょうどノルウエー南北の中間点にあり、多数の島々と船で結ぶ交通の要所とし
て栄えた半島の先にある。 また鉄道路線とも接続しており、南北に走る国道、陸の要
所である<ファウスケ駅>にも近く、観光拠点としても栄えているようである。
いかにもバイキングの住処のような雰囲気を醸す静かな漁港でもある。
肌を刺すような冷たい潮風が、アイスランドの方から吹き付けてきている。
妖精の 住すフィヨルド 雪帽子 實久
バイキング 太古背負いし 雪の谷 實久
白樺に 木洩れ日踊る 北極圏 實久

<ボーデ港散策>

ボーデ港・ノルウエー
Sketched by Sanehisa Goto
始発駅である<ボーデ駅>11時35分発の列車Train#472で、ファウスケ経由、トロンヘ
イムに向かう。
列車での相席のノルウエーの女子学生さん、ローズ嬢とリン嬢からノルウエー人の人生
観や国民性、習慣について聞かせてもらう。 二人は、オスロ近郊に住み、ボーデの
<ジャーナリスト・インスティテュート>に週3日かよっているとのことである。
とくに、世界観としてトルストイの言葉「光あるうち、光のなかを歩め」に話が及び、
北欧青年の宇宙観を聴くことが出来た。
それは、キリスト教化される前のノルド人(ノース人)の信仰に基づいており、興味あ
る話であった。
北欧ゲルマンの世界観では、この世は九つの世界から成るといわれ、
その一つに、神々と混沌による大いなる戦いで、命あるすべての存在が死に絶えるとさ
れた、北欧神話における最終戦争<ラグナロク>という世界観があるという話をしてく
れた。
仏教にも末法思想という考えがあり、「この世の終わり」を意味する終末的思想がある
ことを伝え、お互い「今を生きる」大切さを認め合った列車の旅となった。
バックパッカーとして世界を放浪していると、おのれの齢を忘れ、つい青年の情熱に浸
ってしまうのである。
この列車には、日本では見られない子供車両<Kid‘s Car>を連結しており、内部を見学
させてもらった。
また車窓よりノルウエーの風景をスケッチし、楽しんだ。

フェリーと列車が接続するボーデ駅にて

Train #472 Kid‘s Car
Sketched by Sanehisa Goto

車窓からのNaeroyfjord/ネーロイ・フィヨルド風景

Naeroyfjord/ネーロイ・フィヨルド (車窓からの風景)

トロンヘイム近郊の星空と日の出風景
Train#472の車窓より
Sketched by Sanehisa Goto
列車内での夕食は、バックパッカーらしく、中華のテイクアウト<肉・野菜炒め+ライ
ス>にローズ嬢差入れの生のニンジンをいただく。
目的地であるトロンヘイムには、21:35に着き、オスロ行きの夜行列車に乗り換え
て、翌日朝 07:00 にオスロに着く。
▼ 9/23 列車泊 <21:35着 トロンヘイム 22:30発 ➡夜行列車乗換 ➡翌日07:10着 オスロ>

オスロ➡ベルゲン 特急夜行列車にて
■ 9月24日 夜行列車<オスロ ➡ ベルゲン>
朝一番、食堂車でコーヒーをいただきながら、遠く明けゆくスカンジナビアの峰々の息
吹きを感じ、心の平安と、豊かな恵みに感謝した。 コーヒーを口にしながら夜明け前
のオスロ近郊のスケッチを画き上げた。

オスロ近郊<夜明け前>
Sketched by Sanehisa Goto

ノルウエ―鉄道の特急夜行列車
なんとゆっくりと、心豊かな時間をノルウエーの人々は享受していることか。
静かに自然と溶合い、時の流れに逆らわずに生きている姿に人間としての尊厳を見る思
いである。
同乗のローズ嬢とリン嬢との別れを惜しむ。 ジャーナリストとしての夢が成就するよう
に祈り分かれた。
07:10 ベルゲンへの乗換駅オスロ駅に定刻到着した。
さっそく、駅構内でベルゲン行のサバイバル食料(バナナ・リンゴ・ビスケット・
水 38KR)を調達する。
08:25発 ベルゲン行の列車は、1等車のみの列車編成、それもユーレイル・パスが使え
るという。
ミュージック・イヤホーンサービス、ソフトドリンク・赤ワインサービス、アペタ
イザーとゴージャスなサービスである。
食堂車でいただくランチも、バックパッカーとしては贅沢そのものである。
アペタイザー(サーモン・ブルベリー・ライム)、バター味付きポテト+ローストビーフ、
赤ワイン、フルーツ(オレンジ・ストロベリー・アップル)、パン、バター、ジャム、
コーヒーと、
一流ホテル並みである。


ユーロパス1等車 <夕食メニュー>
ノルウエーの人々、いや北欧の人々は、<生きる喜び>を感じることにたいして貪欲さ
が見られる。 それを成就するための工夫をし、国を挙げて総力を挙げ、全員で勝ち取る
姿勢が凄いのである。
女性70%の就労という男女平等社会の実現、社会保障制度の充実に見る「高福祉・高
負担」の分担、年金制度による老後保障政策の充実など、その社会福祉政策は日本も
見習うべきところが多々あると云える。
高齢少子化を迎える日本には、いまだ25倍の人口を抱えているのである。
ノルウエーは、500万人、東京都の半分以下の人口で<豊かさ>を感じる国造りに励ん
でいるのである。
少し、ノルウエーの生活をのぞいておきたい。
物価で見ると、日本と同じだが、ロシアの倍だろうか。
サンドイッチが49KR(約600円)である。
Credit CardのVISAが使えなくなり、AMEX(アメリカン・エクスプレス)Cardに切り
替える。
女性の化粧は、男女同権を掲げる国らしく、素顔が多く、歩き方もどちらかと言うと男
性的である。
幼児や、子供の育児にも男性の参加が進んでいて、乳母車を押す父親の爽やかな姿が印
象的である。
フロムへの山岳列車乗換駅ミュダール駅手前のFINSE駅付近(12:35)で、「現在、列車
は 1228m 地点を通過中」とのアナウンスがあった。
どうも、ノルウエー鉄道路線の最高地点を越えているようである。
1800m級の峰々は雪帽子をかぶり、観光客を歓迎しているようである。
フィヨルドは、100万年もの長い時間をかけて氷河が山塊を削り、創り上げられた偉大
なる造形作品である。
フィヨルド観光の入口・フロム / Flamへは、トロンヘイムからの道路はない。 複雑なフィヨルドを避けて、列車によりオスロ経由でしか行けない。

乗車路線<ボーデ➡トロンヘイム➡オスロ➡ベルゲン>
Bodo➡Trondheim➡Oslo➡Bergen
ミュルダール/Myrdal駅で、13:30 発フロム/Flam 行の山岳列車、日本からのフィヨル
ド観光の団体客であふれる列車に乗換えた。
山岳列車は、美しいフィヨルドのオンラインにあり、人を近づけさせない岩の塊という
厳しい急こう配を下っていく。 その間、植栽を許さない岩壁からきれいな滝が流れ落
もちろん、この滝は氷河や万年雪の融水である。
よくもこれらの巌岩にトンネルを穿ち、山岳鉄道を敷設したものである。
お召列車のように急こう配のトンネルを潜り抜け、ゆっくりと進む山岳列車は、次々と
景色を変え、楽しませてくれる。 乗客は、自由に席を移動して、氷河や雪渓を楽しむ
ことができる。
秋真っただ中のノルウエーのフィヨルドは、特に紅葉が美しく、目を楽しませてくれ
る。

ノルウエ―・フロム路線最大の滝<ショースフォッセン/Kjosfossen>
ミュルダール / Myrdal駅から、フィヨルド観光の基地フロム / Flam駅へは、標高差900m
を一気にシーレベルまで下る山岳鉄道で、世界で最も美しい路線ともいわれている。
なかでも、途中下車して見せてくれるショースフォッセン(ショース滝)は圧巻であ
る。
フロムを中心とする、世界遺産<ソグネフィヨルド>は、大きな山とフィヨルドですっ
ぽり囲まれたフェリーによる観光拠点である。
また、フロムは、海賊バイキングや北欧神話の雰囲気を残す村で、クラフトビールの醸
造所(エーギル・ブリッゲリーエ社)の建物やその内部のインテリアにその影響を見る
ことができる。
<ソグネフィヨルド観光>
世界遺産である<ソグネフィヨルド>へは、ほとんどが観光ツアー参加の団体客であ
る。
こちらは、単独のバックバッカ―、現地のフィヨルド・ツアーに参加した。


フェリー観光船よりソグネフィヨルド観賞


―観光フェリー & 山岳鉄道列車―
Sketched by Sanehisa Goto

ノルウエ―・フロム線 山岳鉄道列車 17-2227
<Flam ⇔ Myrdal>

Sketched by Sanehisa Goto
観光フェリーによるクルージングから見上げる氷河によって削られた深い谷と、断崖絶
壁の頂に残雪の残る絶景や数多くの幻想的な滝を堪能した。 時間を惜しんでスケッチ
にも励んだ。
フェリーは、約2時間のフィヨルド観光を終え、終着港クドヴァンゲンに到着した。
ここからは、バスに乗換てベルゲン鉄道のボス駅に向かい、 ノルウエーの第二の都市
ベルゲンに立ちより1泊することにした。

バスでクドヴァンゲンよりボス駅に向かう小休止のホテルにて
今夜は、フィヨルド観光の入口でもあるベルゲンの<モンタナ・ユースホステル>に宿
泊する。
モンタナYHへは、路線バス#31で、13番目のバス停で降りる。
▼ 9/24 Montana Youth Hostel泊 (Bergen)

Montana Youth Hostel
Bergen/Norway
■ 9月25日 <ベルゲン➡オスロ>
モンタナ・ユースホステルのドミトリー(6人部屋)では、オーストラリアの青年アン
ドリュー、ビッキー、ジョリー3人組との相部屋である。 彼らはIT企業に勤務し、バケ
ーションをとってスカンジナビア半島を旅行中とのことである。
夕食に招かれ、自炊で作ったベーコン入りクリームソース・マカロニをご馳走してくれ
た。 自分たちでクックしながら旅行を楽しんでいる素敵な青年たちである。
こちらも、赤ワインとチキンサンドを差入れて食卓を飾った。
今朝は、同室のオーストラリアの青年たちに朝早く別れ、ひとりノルウエーの原風景を
楽しむため、駅までの4㎞を、徒歩で2時間かけてゆっくりと散策を楽しんだ。

早朝、ベルゲンの港町を見下ろしながら列車駅に徒歩で向かう

ベルゲンを取巻く氷河をいだく峰々
この海に向かって開けたフィヨルドの街 ベルゲン(ノルウエー第2の都市・35万人)
にも、ここでしか味わえない北欧の生活に出会えた。
まず気付くのが、自転車による通学・通勤の圧倒的な多さである。 <エコイズム>を優
先させ、整然と整理された自転車道の素晴らしさ、ヘルメットの着用、交通規則の徹底
など、車に優先させた思想<ユックリズム>の広がりに目を見張ったものである。 車も
歩行者第一、安全に徹した運転に感心させられた。
また、いたるところで乳母車を押し、公園でブランコを押し、子育てをする多くの
若き父親の姿に出会った。

ノルウエ―・ベルゲン・メルケン街
Sketched by Sanehisa Goto

ベルゲン駅で朝食を
ベルゲン 07:58 発の列車#62 は、オスロに 14:45 に着く。
ノルウエ―の山岳鉄道列車は、氷河を抜けて突っ走り、乗客は好きな席に移動して美し
い雪渓や、氷河を楽しむのである。
9月末のノルウエ―の紅葉もまた素晴らしい。
生きとして命あるこれらの紅葉が一斉に命輝かせるのであるから、言葉では言い表せな
いほどの美しい姿にこころ打たれた。
オスロに着くと、まず今夜の宿となるオスロ・ユースホステル<オスロ・バンドレル・
ハラルズヘイム/Oslo Vandrerjjem Haraldsheim>に向かった。
栄養補給のため中華料理店を見つけるためである。
同じドミトリーに、カナダからの大学生で、1年休学し世界を回っているバックパッカ
ーJohn君がおり、日本語を習いたいとのことで、相手をさせられることになった。
お手玉4個の名人で、握り寿司が大好きであることをテーマに日本語教室がさっそく持
たれた。
▼9/25 オスロ・ユースホステル (ドミトリー160NCR)

■ 9月26日 <列車移動> オスロ(ノルウエー)➡ストックホルム(スエーデン)
列車番号IC50 : オスロ 07:32発 ➡ ストックホルム13:20 着
07:32 発 ストックホルム行列車に乗るため、オスロYHを早めに出た。
しかし、前もって調べておいた市電での移動がストライキで、やむなく市バスに変更す
ることになり、列車に間に合わせるためには随分慌てたものである。
ツアー以外の、単独旅行では、おのれしか頼れるものがないため、前段階でのスケジュ
ール管理と、時間管理は特段に厳守しない限り、旅は頓挫してしまうことになる。
列車・バスは1時間前、飛行機では2時間前には、駅・バスステーション・飛行場に到着
していることが求められるといえる。
ノルウエー通貨―クローネ(NOK)を使い切るために、キオスクでランチ用シュリン
プ・サンドを購入する。
09:35 ノルウエ―/スエーデン国境の街<Charlottenberg駅>を通過中である。
EC(ヨーロッパ連合国)間では、国境が取り払われ入出国の検査がなくなったこと自
体、バックパッカーにとっては有難いことである。
国境ごとに、立ちふさがる難問と時間を乗越えて初めて国境を越えられることを考える
と感無量である。 (2001年当時、EU/ヨーロッパ共同体はまだ結成されていなかった)
10:30 スエーデンに入り、Vanerin Lake(ブエーネル湖)の風景に見惚れた。
さっそく湖面に映る村の景色をスケッチにおさめた。

Vanerin Lake / Sweden
Sketched by Sanehisa Goto
ストックホルム 13:20 着、さっそく栄養補給のため中華<ドラゴンパレス>飛び込
んで<肉野菜炒め・焼き飯・ワンタン>をオーダー、かなりの量なので半分はテイクア
ウトして、夜食に当てることにした。
食べすぎからか、珍しく腹を下す。 どうも生ものからくる細菌性のようだ。 生水には
特に気を付けているが、用心することにした。 ただちに正露丸を放り込む。
洗練されたストックホルムの街に映える夕焼けの美しいこと、見事であり、ロマンチック
である。
教会から流れる鐘の音、真白な月、茜さす夕焼け雲、真白な帆船、たたずむ中世風建築
物など、幸せを表現している町である。
旧市街の街並みも、イタリアのアシジを思わせる職人の街であり、中世風路地裏に魅了
させてしまった。
今夜は、ユースホステルとして使われている、港に錨を降ろした真白な帆船で宿泊する。
多分、夢の中でお伽の国を走り回ることになりそうである。
▼ 9/26 宿泊 <アフ・チャプマン・ユースホステル>
ストックフォルム / スエーデン
磁気カード式ドアーキーを供えた8人部屋(ドミトリー)、ドイツ青年2・イギリスと
フランスの夫婦2組・中国青年・出張中のスエーデン会社員2に、私の8名である。
セキュリティーも万全、シャワー・トイレも清潔だが、ロッカーには持参のカギが必要
である。


YHの帆船 と ストックホルム港
<アフ・チャプマン・ユースホステル>
■ 9月27日 ストックホルム
ストックホルムは、クラッシックとモダンの融合の街である。
緑樹とモダン色、太陽の演出である夕焼けと朝焼けと、すべてにハーモニーで成り立っ
ている。
どこか人間の英知が生み出した都市美の極致と言っても過言ではないであろう。
素敵な街並みである。
そこに住み、維持している人々の豊かさとゆとりを感じた。
コペンハーゲンに向かうユーレイルに乗る前に、ストックホルムの街を散策し、スケッ
チに励んだ。
いよいよ、スカンジナビア半島の北ヨーロッパから、中央ヨーロッパである西欧、東欧
へ向かう。
北欧から西欧へ、ストックホルムからコペンハーゲンへは、橋で渡るのだから驚きである。
フェリーで渡るものとばかり思っていたからである。

港に囲まれたストックフォルムの美しき街
Sketched by Sanehisa Goto

ストックホルム港の浮かぶ真白なYH帆船 と ストックホルムの街
スエーデン国旗
■ 9月27日 列車移動 <ストックホルム ➡ コペンハーゲン>
中央ヨーロッパは、バックパック(個人旅行)や家族旅行、ツアーなどで何度も訪問し
ているお馴染みのエリアである。
計画を立てるにあたって、ヨーロッパはユーレイルパスを使っての鉄道利用と決めてい
た。
ユーレイルパスは、現地での購入は不可能なので、日本で購入することとなる。
また、鉄道に興味があるので、出発前に列車や機関車、路線、時刻表などを随分と調べ
たものだ。
いつものことだが、海外で巡り合った機関車や列車の写真を撮るため、またスケッチを
したりして、時には列車に乗り遅れたりもした。
まずは、ヨーロッパを走っている主な高速鉄道をみておきたい。
<ヨーロッパの特急列車> (2023年現在)
- ユーロシティ(EuroCity)
西ヨーロッパでは高速鉄道網の発達により減少傾向にある。
一等車と二等車の双方を連結している。
最高速度は200km/h以下であり、ICEなどの高速列車の運行されている国では、
これらに次ぐ種別と位置づけられている。

ユーロシティ(EuroCity)
ヨーロッパ各国の主に在来線において、その都市間連絡を主たる目的として運行される。
JRの特急列車に近い。

最高速度は約300kmで運行しており、ベルリンやハンブルク、ケルンなどの都市間を移動するのに
非常に便利。 ICEはドイツ国内だけではなく、デンマークやオランダ、フランス、ベルギー、
オーストリア、スイスへの国際路線にも乗り入れている。

インターシティーエクスプレス(InterCity Express)
ドイツ高速鉄道
- 旧タリス(Thalys) ユーロスター(西ヨーロッパ)
車体・内装ともに赤を基調とし、パリ~ブリュッセル間を約1時間25分で1日最大24便が運行

旧タリス(Thalys) ユーロスター(西ヨーロッパ)
ヨーロッパ周遊旅行におすすめの鉄道は「TGV」。フランス国鉄(SNCF)が運行する超高速鉄道。
最高時速約320kmで、日本の新幹線の記録を世界で初めて超えたことでも知られています。

- ユーロスター(EuroStar)
ドーバー海峡トンネルを通ってイギリスとヨーロッパ大陸を結ぶ高速鉄道「ユーロスター」。
1994年に開通してから、徐々に運行スピードを上げ、現在ではロンドン~パリ間を毎時300㎞の
速度で約2時間20分で運行。

ユーロスター(EuroStar)
- イタロ (ITALO) イタリアの高速鉄道
イタリアの主要な都市であるローマやミラノ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ナポリなどを結んで
いる。

イタロ (ITALO) イタリアの高速鉄道
- アヴェ(AVE) スペインの高速鉄道
AVEはスペインで有名な高速鉄道で、マドリッドを中心にバルセロナやコルドバ、セビリア、
バレンシア、マラガなどを結んでいるのが特徴。
最高時速約310kmで運行しており、スペイン国内を快適に移動できる。

アヴェ(AVE) スペインの高速鉄道
- ベルニナエクスプレス
ベルニナ急行も氷河急行と同じく、スイスで人気のある観光鉄道。
観光名所のサン・モリッツ周辺を走っており、複数のルートがあるのが特徴。

ベルニナエクスプレス
氷河特急は、スイス旅行で人気の観光列車。ツェルマットとサン・モリッツを運行しており、
スイスアルプスをゆっくりと横断、約8時間の旅を楽しめる。

- SJ2000/SJ3000 (スカンジナビア特急)
スウェーデンを代表する高速列車。
振り子式の列車で、カーブでもスピードを落とさずに最高時速約200kmで走り抜ける。

SJ2000/SJ3000 (スカンジナビア特急)
<ユーレイル・パスの利用>
ひとつの共通レールパスでヨーロッパ中を旅行できるので、バックパッカーにとって便
利である。
ユーレイル・パスは、ヨーロッパ各地のほとんどの列車をフレキシブルに利用できる
オールインワンの鉄道チケットである。
従来の鉄道チケットとは異なり、ユーレイルならいつでも好きな場所へ行ける。
➀1枚のレイルパスで33か国をカバーしている。
②新しい列車、バスやフェリーに乗車/乗船する前に、ユーレイル・パスの<旅行欄>
に旅の詳細<出発時間、出発駅、到着駅>を必ず記入する。
検札係は、記入したパスを確認して、その区間を有効とみなす。
➂ユーレイルパスには座席の予約は含まれていないが、少額の予約料金で席を
確保できる。

EuRail Pass / ユーレイルパス(みほん)
陸路で、次なる目的地イギリスに行くには、一度ヨーロッパ本土(デンマーク・
オランダ・ドイツ)を通って、ドーバ海峡をくぐっていくことになる。
もちろん、ヨーロッパ全線共通の<ユーレイルパス>を使ってである。
途中、デンマークのコペンハーゲンに立寄り、ドイツのケルンでユーロスターに
乗換えてイギリスに向かった。
12:40 列車は、カテガット海峡に架かる鉄橋を渡ってコペンハーゲンに向かっている。
スカンジナビア半島と、中央ヨーロッパが橋で結ばれていることに驚いたものである。
中学時代の地理の本を見ていた限り、スカンジナビア諸国はバルトの海峡を挟んで遠く
離れていたものとばかり思っていたからである。
コペンハーゲンに向かって、左側がバルト海、右側が北海という狭い海峡の鉄橋を列車
は走っているのだから不思議に思えた。
この海峡は、地中海の出入り口のジブラルタル海峡と同じく戦略的に重要な地点でも
ある。
ロシアの潜水艦にとって、バルト海から大西洋にでるただ一つの出口であり、よく事故
を起こすことで知られている。
13:30 あれこれ考える間もなく、デンマークの首都コペンハーゲンに列車は到着した。
まず目にしたのは、筋肉流々とした男性的なご婦人である。
もちろん北欧と同じく、大抵の女性が化粧をしていないのにも驚かされた。
ファッションは、主にジーンズで、カジュアル・スタイルであり、働く女性としての
動き易さを尊重しているようである。
駅のロッカーに荷物を預け、チボリ公園に寄るが残念ながらこの日は休園日。
しかし、ロシア・シベリアのウラジオストクをでて、どちらかと言えば、カントリー的
風景や、素朴な人間に接してきただけに、オスロ、ストックホルムから、いきなりヨー
ロッパの中心に飛び込んだものだから、大都会の雑然さと言おうか、人間の坩堝にいき
なり飛び込んだという錯覚に落ち込んだのである。
人間があまりにも多すぎる。
それも、広大なシベリアや、スカンジナビアという大自然を潜りぬけてきたバックパッカー
にとって、都会の人々のちょっぴり汚れた生態にすこし違和感を覚え、文明の煩雑さに少し
疲れたものである。
デンマークも、フィンランド・ノルウエーやスエーデンと同じく、男女同権・自由平
等・高福利厚生という点で見る限り、デンマークも北欧に属するように思えた。
一方、コペンハーゲンに入って、浮浪者や第三国からの出稼ぎの人々が多く目につき始めた。
街角の広場<Herlev Place / ヘアレウ広場>に腰を下ろし、人々を観察しながら尖塔が
立ち並ぶ街並みをスケッチした。

<ヘアレウ広場 / Herlev Place>
Sketched by Sanehisa Goto
人間の醜さにくらべ、中世的な建物に囲まれた歴史の街コペンハーゲンは、歩行者天国
や、立ち並ぶ教会の尖塔に何とも言えない包容力が感じられ、安堵したのである。
コペンハーゲンより、ドイツ・ケルンへは、もちろんユーレイル・パス利用の高速鉄道
での移動である。
コンパートメントには、2人用のクシェットと6人用があり、疲れをとるため2人用を利
用した。
夜中、トイレに立った時に6人用をのぞく機会があったが、酒盛りに興奮、大声で<オ
オソレミヨ>を合唱し、どんちゃん騒ぎである。 どの国の青年も皆同じである、若さ
の特権を謳歌している姿に妙に拍手を贈ったものである。
ベットメーキングは、車掌に任すこと。 日本のように自分でベットメーキングしてい
たら、車掌に自分の仕事をとるなと、真赤な顔をして注意されてしまった。 何か、ド
イツ人の職業意識であるマイスター精神の片鱗をかいま見た気がした。

ヘアレウ広場にて
▼ 9/27 列車泊
高速鉄道移動 <コペンハーゲン / デンマーク ➡ Kolo“n / ケルン / ドイツ>
・ハンブルグ経由 645㎞
(注意)ベットメーキングは、車掌の役目
・海峡横断は、列車ごとフェリーで渡る
■ 9月28日
ケルン / Kolo”n は、ボン(旧西ドイツの首都)の郊外にあり、ヨーロッパ鉄道網の中
心的位置にある。
コペンハーゲンからの高速鉄道は、憧れのタリス(Thalys)であった。
ケルン到着前にでた朝食(1等車のメニュー:菓子パン・ジャム・バター・ヨーグル
ト・オレンジジュース・コーヒー)をとりながら、ケルン到着時の高速列車タリスの
顔写真撮りの準備にかかった。

憧れの高速鉄道<タリス>と共に (ケルン駅で)

高速鉄道<タリス>1等車クシェットで朝食
今朝のファイナンス・タイムス紙によると、この先に訪ねるスイスで手榴弾による15人
死亡、14人重傷という無差別殺人があったと報じていた。
地球どこにも安全地帯はないといバックパッカーの鉄則を確認し、自分は自分でしか守
ることができないという覚悟を新たにした。
ケルンでユーロスターに乗換えて、イギリスに向かっている。
ユーロパスを100%使い切るために、ヨーロッパは鉄道旅がメインになることは致し
方がない。
鉄道の旅をエンジョイすることに集中することにした。
12:15 ユーロスターが、ドーバー海峡のトンネルに突入した。
アメリカでの同時多発テロ9:11の影響であろう、英仏トンネルの爆破を恐れてか、
空港と同じく厳しいボディチェック、手荷物検査が行われていた。
12:30 高速鉄道ユーロスターにより約15分でドーバー海峡を通過したのだから、
18年前の家族旅行で船によるドーバー海峡横断で約6時間もかかった記憶が懐かしく
よみがえった。

ユーロ―スター/EUROSTAR Train#51
Sketched by Sanehisa Goto
ロンドンに到着し、ユースホステル や ゲストハウス(最低23£)をあたったが、宿泊
費が高く、学校関係者に解放されている<国際学生ハウス>(16£)に投宿することとなった。
原則として、バックパッカー精神として、<Cheap Is Best>に従うことにしている。
▼9/28 国際学生ハウス<International Students House> 連泊
23D Tavistock Place, London WC1H 9SE, UK
連泊するので、旅の汚れに音を上げている衣服・下着・靴下などを洗濯することにした。
その上、シャワーにも時間をかけて、旅の垢を洗い流した。

ロンドン国際学生ハウス
■ 9月29~30日 <ロンドン滞在>
朝一番、ロンドン観光前に、ハウス近くのキングス・クロス駅で、明日からの
ユーレイル・パスによるスコットランド周遊の予約をとった。
ロンドンブリッジ・タワーブリッジ・ロンドン塔・ロンドン大英博物館を歩いて回った
が、どっと疲れが出たので、ハウスに戻ってひと眠りである。
世界遺産<ロンドン・ブリッジ>は、城塞として建てられ、王宮に使われたり、造幣
局・銀行・動物園を備えたりした後、政治犯の収監所や、犯罪者の処刑所として使われ
たという。
現在もイギリス王室が所有する宮殿である。
途中で気になったことがある。
男性用の便器が高く、つま先立ちでやっと届くというその高さに閉口した。
それも一人用の便器ではなく、長い飼い葉桶に台をつけた便器に出会って驚かされた。
なんといっても、並んでの立ちションは落ち着かなく、不発におわることもあった。

ロンドン公衆トイレ<飼い葉桶タイプ>
大英博物館では、アングロサクソンの偉大さ、それも植民地や侵略の歴史からくる略奪
の展示と、その植民地からの作品の多さに少し嫌気がさしたものである。

アレンジされた<双頭の蛇>
大英博物館再訪時 2006年
Sketched by Sanehisa Goto
一方、アングロサクソンの生立ちを詳しく学ぶことが出来た。
アングロサクソンであるロンドンっ子は、ローマ帝国が退散後、入って来たゲルマン人
(デンマーク・ドイツ北部)によって引き継がれた子孫であるという。
ただ、ロンドンが、2000年前のローマ帝国によるロンディニウムが創建の起源であると
いい、紀元200年ごろには、ローマ支配のもと、すでに60,000人を擁する都市を形成し
ていたというからずいぶん古い街であることには驚かされた。

ロンドン塔前で

タワーブリッジ前で

<タワーブリッジ>
ロンドン・イギリス
Sketched by Sanehisa Goto
▼ 9/28 国際学生ハウス<International Students House> 連泊
■ 9月30日 ロンドン散策(二日目)
<国際学生ハウス>は、学生だけでなく、学校関係者も広く利用することができる。
ある私大と国立大に関係していた関係で、ロンドンでの宿泊はこれで2度目である。
旅行者だけでなく、留学生の寮としての役目も果たしているようで、長期滞在者が
目立っていた。
同室のイタリアからの青年 マリオ君は、職探しのため利用しているという。
イングランド向け出立の準備を終え、散策コース<ビックベン・国会議事堂・ウエスト
ミンスター寺院>へ出かける。
ウエストミンスター寺院では、40名ほどの礼拝者と共に、祈りを捧げ、祝福を受けた。
日曜日だというのに礼拝者が少なく、静かな日曜礼拝であった。

ウエストミンスター寺院での礼拝を終え

国会議事堂<ビックベン>を背に
北から南へヨーロッパを下りて来るにつれ、その人間模様も変わってくる。
北欧の方が、人間としてより誠実であり、勤勉であり、清潔であり、計画的である様に
見受けられる。
ここ英国は、島国であり二度の世界大戦にもかかわらず、徹底した破壊を免れているか
らか、17世紀風の建物が残り、帝国時代の生活が続いているような気がしてならない。
気候もそうだが、どんよりと曇った、どこか暗く陰湿な風景に飲み込まれていくような
気がしてならない。
ロンドンっ子は、このようなありのままのロンドンがお好きなようである。
家一つとっても、個性ある家や、ストリートハウスを見かけることなく、くすんだレン
ガ造りの建物が機械的に並んでいるのだから、恐らく行政の指導によるものであろう。
島国ブリテンは、火山国のイメージがない。
日本のような山脈がなく、北海道のように大平原が定規で線を引いたように整
然と区画されて、見事である。 アングロサクソンによって成立したカナダ、オースト
ラリア、ニュージランドでもよく似た光景を目にしてきた。
▼9/29 国際学生ハウス<International Students House> 連泊
■ 10月1日 列車移動 <ロンドン ➡ キール・ロチェス>
コンチネンタル・ブレックファースト(ハム・チーズ・・ミルクティー・オレンジジュ
ース・ブレッド・バター・ジャム)をいただきながら、国際学生ハウスを利用している
老夫婦が、人生を質素にエンジョイしている姿を、微笑ましく眺めていたものである。
お二人は、多分教師であったと思われる。
その柔和なお顔にどこか優しくも、信念に燃えるきりっとした目の輝きに、今なお教師
としての姿が残っていた。
日本の私学共済組合にも見られるように、英国でも教職を終えられた方々への福祉事業
が進んでいるようである。
人生の旅を終えようとする数組の老カップルが、静かにお互いの長年の苦労を労わりな
がら朝食をとっておられる姿に、成熟しきった英国の落日の姿を重ねていた。
《ロンドン・キングクロス駅 09:00発 ➡ 13:21着 <エジンバラ駅乗換> 13:34発 ➡ インバネス駅 19:27着》
エジンバラ / Edinburgh行のスコット・レイルに乗車し、エジンバラで乗換て、インバ
ネス/Invernessに向かう。
ネッシーが棲むと云われるネッシー湖の、小雨煙る幻想的な風景を楽しみながらの列車
の旅である。
旅立つ前に想像した風景が眼前にあるが、この水深のない湖にはたしてネッシーと言う
幻の生き物は生息しているのだろうか。 いや、いるという夢物語にどこか日本の桃太郎や
竜宮城やかぐや姫の物語が重なり、童話であり夢物語だからこそ楽しいのであろう。

車窓よりネッシー湖を眺める
列車は、これよりローランドからハイランドに入っていく。
ロンドンのキングクロス駅を出てから、ずっと平原であったのだが、遠くに山の姿を見
つけて、懐かしく日本を思い出したのである。
イングランドでは、くすんだレンガ色の家ばかりであったが、スコットランドでは黒い
屋根に白壁へと変わるのである。
波打つ緑の絨毯に、背中に赤いマークを付けた羊たちが、太陽の恵みを受けて長い影を
作っていた。
19:17 約10時間のイギリス縦断列車の旅を終え、まだ明るさが残るインバネス
駅に着き、さっそく予約しておいたインバネス・ユースホステルに落ち着いた。
▼10/01 宿泊 Invernes Youth Hostel (インバネス・ユースホステル)

Inverness Youth Hostel
インバネスのユースホステルでは、ドイツからのサイクリング・ペアーと同室。
情報交換をしながら、お互いの手料理カレー<チキンカレーと ベジタリアン>を半分づ
分け合って、夕食をとった。
ドイツは、ワンダーフォーゲル(渡り鳥)運動発祥の地であり、若者たちはリュックを
担ぎ世界中を旅してまわる。 その土地の自然や、歴史に対する知識も豊富で、政治情勢
にも敏感である。各国にあるドイツ大使館には、バックパックする青年たちの避難宿泊施
設も併設されているという。
自国の青年たちのワンだフォーゲル運動を助け、またその地での紛争や騒動に巻き込ま
れないようにするためだという。
日本の現地大使館も、邦人保護や救済を担っており、バックパッカーとして万一の危機
にはお世話になれることを知っておくとよい。
これまでの旅では、かかる危機に直面することもなく無事であり、幸いにも現地大使館
にお世話になったことはない。
■ 10月2日 英国内移動日 <インバネス/Inverness ➡ グラスゴー/Glasgow>
インバネス/Inverness(列車)➡ Kyle of Lochaish (フェリー) ➡
Broadford(フェリー)➡ Mallaig(列車)➡ グラスゴー/Glasgow
次なる訪問国アイルランドへの中継地であるグラスゴーへ向かう。
インバネスより、カイル・オブ・ロカルシュへの列車では、マンチェスターからの
老夫妻と楽しい時間を過ごした。
彼らはツアーに参加し、スカイ島を周遊するという。
スコットランドでは、老夫婦のほほえましい旅姿をよく目にする。
お二人して寄添って、人生を楽しんでいらっしゃる。
それも、夫である男性がみなお洒落であり、生き生きとお歳をとっているのに対して、
奥さんの方は少しお疲れなのか、年相応の地味な恰好をされているのが対照的である。
グラスゴーへの行程は、スコットランド最北のスコットランド・レイル(鉄道)の一つ
カイル・オブ・ロカルシュ行の列車で終点まで行き、フェリーでスカイ島ブロードフオ
ード港を経由してマレーグに向かう。
マレーグからは、列車に乗り換えて、グラスゴーに向かうのである。
スコットランドのよく手入れされた自然を楽しめる列車、フェリーの旅である。

車内吊ポスターの<バイキング>をスケッチする
バックパックの旅は、ツアーと違い、おのれの行きたいところへ、時間に左右されず
に、好きな乗り物を選んでコースを決められるところにある。
この旅も、地方の列車や、フェリーに揺られて、スコットランド北部の田舎の景色や生
活をのぞきながらのんびりと旅を楽しんだ。

イギリス最北路線の一つ<Kyle of Lochaish / カイル・オブ・ロカルシュ>行の列車で
時には、第一線から引退してもよいと思われる、古き良き時代のSLに出会ったりと、鉄道
マニアにとって新しい発見をすることもある。 マレーグでは、出会ったSLに群がるマニ
アの真剣なまなざしに、こちらも乗車列車を見送ってまで、スケッチに興奮したもので
ある。

SL62H5/620D5
West Cost Line – Scot Railway
Mallaig Station
Sketched by Sanehisa Goto


現役で走り続けている<Jacobite Steam Train>
West Cost Line – Scotrail
Near Mallaig Station
グラスゴー行列車、West Cost Line – Scotrailwayの車窓からの風景は、まるでチベッ
ト高原をトヨタのランドクルーザで横断したときに出会った風景によく似ているので驚
いたものである。
僅かの草が、小川の周りに見られるのと、木が一本も生えていないところがそっくりで
ある。
お城の周りの緑に出会って、驚きのペンを走らせたほどである。
後で調べて分かったことだが、このダンフタフナージ城 / Dunstaffnage Castleは最古
の石造りの城(13C)として有名らしい。
イギリスを旅していて、ロンドン以外でめったに黒人のひとに出会わなかったことに
違和感を持った。 特に、列車の長旅で一人として見かけなかったことに驚いている。
アメリカに長年住んでいた者にとっては、不思議にさえ感じたものだ。
それもそのはずである、イギリスは多民族国家として成り立っている割に、全人口に占
める黒人の割合は2001年当時、の総人口約5878万人に対し、黒人系約114万人
(1.95%)に過ぎないのである。 ちなみに、アメリカは12.00%である。
歴史的には、ローマ時代から英国で黒人は市民権を得ていたというのにである。
一つの課題が突き付けられたような気がした。
過去の奴隷貿易との関係があるのだろうか・・・それとも国家政策か・・・

ダンスタフナージ城 (Scotrailの車窓より)
Oban近郊
Sketched by Sanehisa Goto
スケッチ2点 <SLとお城>を仕上げているうちに、マレーグ 16:08発 のスコット・レ
イル の ウエスト・コースト・ラインの列車は、7時間の旅を終えて、グラスゴー
に23:00頃着いた。
夜遅くグラスゴー駅に着いたので、急いで駅近くにあるユースホステルに直行した。
▼ 10/02 <Glasgow Youth Hostel>泊
7/8 Park Terrace, Glasgow G3, 6BY

グラスゴーYH
■ 10月3日 移動日
グラスゴー(列車) ➡ Stanrear(フェリー) ➡ ベルファースト(列車) ➡ ダブリン(アイルランド)
グラスゴーは、昨夜から暴雨風。
ユースホステルの窓は強風に一晩中悲鳴を上げていた。
昨夜、6人部屋のドミトリーを独りで占めていたので、洗濯を済ませて眠りについた。
しかし、深夜、強風の中を3人のホステラーが到着、ドミトリーが急に騒がしくなり、
寝るに寝られず夜を明かしてしまった。
バックパッカーが利用するユースホステルは、ゲストハウスとも違って、格安の宿代で
ベットを提供する代わりに、ドミトリーと言う数名の相部屋を提供するのである。
もちろん、シャワーやトイレは外付けである。
朝食代は、ホステル代に含まれるのが一般的である。
最近、世界各地のユースホステルでは、YMCAやYWCAと同じく、老夫婦が青春の追憶
を楽しんでいる姿が多く見受けられる。
また、学生や社会人の宿舎として長期滞在する者にも利用されていることが多い。
ユースホステル利用の利点は、格安の宿泊代はもちろんだが、世界中の旅行者と情報を
交換でき、旅行する先の国々の政治・世情・危険度などの情報をリアルタイムに収集で
きる利点がある。
また、時にはペアーを組み国境や、危険地帯を突破したり、グループを組み危険に立ち
向かったりと、ひとりでの行動に困難が生じた場合の安全保障として互いに助け合うので
ある。
かような仲間を見つけるためにもユースホステルは、バックパッカーにとってのオアシ
スといえる。
昨夜、鉄道グラスゴー駅から、ユースホステルへの道順を間違えて、チェックインに遅
れてしまった。
一人旅では、必ず自分のいる位置を確認しておくことである。それも自信過剰に陥ら
ず、周囲の人に確認することである。
磁石による確認作業には自信があるはずなのに、時として正反対の方向に歩いている
ことがある。
時々、方向音痴に落ち入るから、旅の途次では十分注意しているのだが・・・
この旅の終着、ケープタウンまでまだまだ気が抜けないのである。
今日は、グラスゴーを出発し、ベルファースト(北アイルランド)経由、アイルランド
の首都ダブリンまでを旅する。
グラスゴーを出発した列車は、地平の彼方に消え入るように見える丘陵地帯、緑の絨毯
を駆け抜けていく。
日本ならば、丘陵を削り、棚田し、水田を作るところだが、英国では森林を伐採し、牧
草を植え、ところどころに群れる羊や乳牛を放牧している。
なんと贅沢な土地利用だろうか。
Stanrear/スタンリア駅より、Cairnyan/ケイルニャン港へ移動し、フェリー<Stena Line>で
ベルファーストに渡る。
英国内乗り放題の<ブリティッシュ・レイル・パス>(British-Rail Pass)は効かず、
31£を支払うこととなった。
英国領ではあるが、ノースアイルランドは独立体として、扱われているようである。
ダブリン行列車にも、ブリティッシュ・レイル・パスは使えず、11.4£を支払う。
<フェリー/Stena Line : Cairnyan港10:00発 ➡ 11:50着Belfast>
日本でいうフェリーの感覚ではない。 浮かぶ豪華なカジノ・ホテルと言った趣がある。
それも高速で運行し、約2時間弱の所要時間にこのような大型フェリーが必要なのだろ
うかとも思った。
やはり、膨大な観光客の往来に見合ったフェリーなのであろう。

フェリー・ルート・マップ (Cairnryan/ケイルニャン ➡ Belfast/ベルファースト)

To Belfast(Stena Line) Ferry

ダブリン行国際列車(ベルファースト駅)
先にも述べたが、北アイルランドは英国領であるにもかかわらずブリティッシュ・レイ
ル・パスが使えないという複雑なお家事情があることに触れたが、もう少し英国と北ア
イルランドについて触れておきたい。
イギリスを構成する4つの地域<連合王国>の中の1つである<北アイルランド>は、ア
イルランドが1920年代にイギリスから独立する際、プロテスタント(新教)とカトリッ
ク(旧教)という宗教や立場の違いから、イギリスに留まった北部の地域である。
1960年代後半から始まった新旧の武装対立、多数派の新教<プロテスタント>と
少数派の旧教<カトリック>間の宗教的対立や、差別問題から生じた対立は、3500人もの
犠牲者を出し、1998年の<ベルファースト合意>をもって終結した。
この旅は、対立終結3年後の訪問であり、ベルファースト訪問を危惧したが、バックパ
ッカーの<見てやろう>精神をかえって刺激してくれたものである。
ベルファーストには、今なお新旧両グループを隔てた壁も残っているが、新旧両住民の
感情はともかく、表面上は、観光化して平和な光景を見せていた。
ダブリン行の国際列車に乗るまでのわずかな時間、ベルファースト散策を楽しみ、スケ
ッチに筆を走らせた。

北アイルランドの位置
(アイルランドの東北部)

英国POST
Illustration by Sanehisa Goto

ベルファースト動物園
Belfast Zoo・Northern Ireland
Illustration by Sanehisa Goto
この<ベルファースト合意>によって、はじめて北アイルランドは正式に英国の一部となった。
現在では、住民のイギリスとアイルランドの二重国籍も認められているという。
ベルファーストの住民に苦節を越えて、ようやく笑顔が戻ったように見えたものである。
宗教間の対立が、住民間の陰惨な殺戮を繰り返してきたことを歴史は見てきている。
ダブリン散策のあと翌日は、ツアー(25£)に参加し、世界遺産<タラの丘とニューグレンジ遺跡>
を見て回った。
▼ 10/3 <Isaacs Hostel Dublin> 泊
2-5 Frenchmans Lane Dublin 1

Isaacs Hostel Dublin
■ 10月4日 ダブリン2日目 (観光後 列車移動) 小雨後曇
<世界遺産 タラの丘 & ニューグレンジ遺跡> ツアー参加
ケルト人の聖地として知られている世界遺産<タラの丘>、ケルト音楽に魅了されてい
る者として持参のCDを耳に、エンヤの代表曲であり、幻想的で神秘なるケルト音楽
Shepherd Moonほかを楽しみながら、ケルト的世界観に浸った。
このCDは、元職場のこころの友よりメモリアル・デーに贈られ、長年、聴くたびに癒され
てきた大切な宝物である。 この旅でもiPodに取入れお守りのように持ち歩いている。
ここケルトの郷で、エンヤのケルト・スピリットを耳にしながら、至福の時間にひたった。

友より贈られたケルトの精神世界を歌い上げているエンヤのCD
いまから300年前に発見された5000年前の先史時代の古代遺跡<ニューグレンジ>は、
エジプトのピラミットや、メキシコのテオティワカン(太陽のピラミット)などと同じ
く、誰が造ったのか、どんな民族が住んでいたのか、なぜ滅亡したのかなど、解明に至
っていないことが多く、今なお研究が続けられている。
古代遺跡<ニューグレンジ>の巨石への渦巻彫刻もまた、宗教儀式と天文学、とくに太
陽による生産暦<カレンダー>として利用されていたと思われる。
1年で最も日が短い冬至の明け方、太陽光が長い導入路に真っ直ぐ入射し、部屋の床を
短時間照らすように建設されている。
ギザのピラミットや、マヤのチチェン・イッツァ、インカのマチュピチュほかでも同じく
太陽神を生活の中心に据えている文明が多くみられる。
果たして各遺跡に同時性があったのかとの考古学的考察がいまだなされている所に
興味が尽きないのである。
あくまで推測だが、現代人に劣らない人類が存在していて、地球変動で絶滅したあと、
現代人が誕生したという説である。
例えば幻のアトランティス大陸に関する神話や、先の古代遺跡にみられる天文学や、
土木工学など現代科学を駆使しても解明できない多くの謎が存在することである。
そこから、宇宙人による地球基地の建設が進んでいたのではないかとの説もあるほど
である。
なんとロマンに満ちた先史物語のなかに、我々生きているのだろうか。
この地球を放浪していると、多くのロマンあふれる史跡に出会えるのである。
今また、世界遺産<タラの丘>や<ニューグレンジ遺跡>に立って、
ロマンに夢を馳せてみたのである。

<タラの丘>のモニュメントと

タラの丘/Hills of Tara
Illusutration by Sanehisa Goto

世界遺産:ニューグレンジ遺跡のある<緑の丘>にて


世界遺産ニューグレンジ遺跡 ニューグレンジ遺跡入口にて
<ストーンの渦巻彫刻>

世界遺産:ニューグレンジ遺跡<ストーンの渦巻彫刻>
Sketched by Sanehisa Goto
<古代遺跡の同時性>
紀元前、BC5000年以上の前の墓墳に、12月21日の冬至の太陽が、正確に墓の中の部屋
を照らし、翌年の豊作を祈るという天体幾何学の知恵は、先に述べたようにマヤ文明の
ピラミットや、アンデス・ペルーのインカ文明、メソポタミア、エジプトのピラミット
などの建築技術に、天文学を採り入れていたことに驚くのである。 それも、全世界を
カバーするコミュニケーション・ツールのなかった古代に、かかる天文技術と言う最高
の知識が全世界的に存在していたのである。
ニューグレンジ遺跡とともに、ユーラシア大陸の最果ての地<モホの断崖/Cliffs of
Moher>の沖、大西洋の海底にプラトン提唱の<幻のアトランティック大陸>が沈んで
いるという夢のある仮説の地をのぞいてみたいという気持ちがわき上がって来た。
<アイリッシュの自然環境との共存>
アイルランドのトイレに入って驚いたことがある。 手洗いに液体ソープではなく、粉
石鹸が置かれていたことである。 環境に優しいと言うことだが、アイリッシュらしい
とおもったものだ。
アイルランドでは、自然環境の多様性、権利について長年議論が続けられてきたという
歴史がある。
空気や水などの「自然」は人間のように、生まれながらの権利を持つようになるかもし
れない。 自然が生存・繁栄・永続する権利、自然環境が劣化したときに修復される
権利、そもそも自然環境が劣化しないよう守られる権利など、さまざまな権利が考えら
れるというのである。
人間は、安全で健康的な自然環境のもとで生活する権利を得るためにも、人間が自然の
声に耳を傾けることが求められていると言える。
昼頃、ダブリンのアイザック・ホステルを出て、アイルランドを列車<アイリッシュ・
レイル>で横断し(186km)、西海岸のGalway/ゴールウエイ向かった。

<アイリッシュ・レイル>
<アイルランド横断鉄道 ダブリン11:25発➡ゴールウエイ13:40着 186㎞>
Sketched by Sanehisa Goto

IÉ22 000系列車(アイリッシュ・レイル)ダブリン近郊線


アイルランド国旗 と 聖句
エンヤのアイリッシュ魂のこもった曲を聴きながら、アイルランド大草原を西海岸に向
かう列車の旅は、最高である。 同じ島国でありながらこの緑の大平原は、日本では決
して味わえない風景である。
また、昨夜のアイリッシュのパブでの生演奏、それも地域の住民が楽器を持って集ま
り、地ビールである黒ギネスのジョッキ―を片手に合唱するさまもまた、日本では味わ
えないアイリッシュの世界である。
車窓から、緑の草原に悠々と草を食む羊や、乳牛たちを眺めながら、パブで歓迎し、演
奏してくれた童謡<夕焼け小焼け>を思い出し、アイルランド人のフレンドリーな、人
の良さを思い出していた。
▼ 10/4 ゴールウエイ(アイルランド西海岸の中心都市)
<CELIC HOSTEL> 泊 ドミトリー@13£
駅を出て、左へぐるっと回って、突当りを右へ200m

<CELIC HOSTEL>ゴールウエイ
とても清潔で、静かなホステル。 さっそく街に出て中華食材を仕入れ、食堂で夕飯を
作っていると、その強烈なニンニクの匂いに、オーナーから苦情、窓を開けての料理と
なった。
購入食材の、モヤシ・玉ねぎ・ニンジン・ピーマン・マッシュルーム・サーモン・ハムに
ニンニクと携行醤油とスパイシーで味付けする。
ご飯は、携行アルファー米にトマトベースのフライドライスを作る。
飲物は、もちろんギネス黒である。
久しぶりの豪華な夕食となった。
この日は、体を休めるための時間をとっていた、いや、ちょっとしたミスから時間が
出来てしまったので、購入したハサミで一か月ぶりに散髪を済ませる。
もちろん洗濯も、だ。
■ 10月5日 ゴールウエイ (アイルランド最西端の街)
昨日は、自信からくる、うっかりミスで朝一番の列車に間に合わず、昼頃の列車に飛び乗
って、ここ<モホの断崖>の基地ゴールウエイに13時51分に着いた。
さっそくインフォーメーションに行ってみたら、なんとすでに冬スケジュールに代わっ
ていて、<モハーの断崖>へは1日1便になっていて、その1便がすでに出発した後であ
った。
これは、神様の「疲れをとるため、少し休め」とのメッセージと受取り、駅近くのセリ
ック・ホステルに泊ったことは、すでに述べたとおりである。
今日は、一日遅れのスケジュールを取り戻すため、ゴールウエー/Galway ➡モハーの断
崖/Cliffs of Moher ➡ Tralee ➡ Limerick ➡ Waterford ➡ Rosslare まで行くこ
とにした。
いよいよ、古代史以前の人類の存在を信じ、<モハーの断崖/Cliffs of Moher>沖、
大西洋に沈んだという<幻のアトランティス大陸>との対面である。
<先史人類と星座言語学>
先でも述べたように、古代史以前にも、現代に劣らない知識や技術を持った先史の人類が
いたと言うことを信じているひとりである。
当時のコミュニケーション言語は、<星座を読み解く宇宙言語>であったと仮説を立てて
みるのも面白い。
天文学・建築学・占星学・太陽神学・運命学・生命誕生学・天体測量学・天道信号学・
時空計測学・真理学・頭脳コンピューター学などで構成されていたのではないだろう
か。
当時の人類は、天体・星座と密接にコミュニケートし、一つの星座言語学を共有したと
想像してみた。
また、彼らはナスカの地上絵に見られるように、宇宙人との交流もあったのではないだ
ろうか。
いや、すでに宇宙人が地球に住み込み、ナスカの地上絵を描いたのではないだろうか。
そう、先の人類が、天文学・土木学などを宇宙人から学んだと思えば、おおくの疑問も
解けてくるように思えるのだが・・・。
では、<モハーの断崖/Cliffs of Moher>をバスツアーで訪ねることにする。

<モハーの断崖> バス・ツアーコース
(Galway発コースに参加)
<モハーの断崖/Cliffs of Moher>
日本から見て、地球の最西端にあるモハーの断崖は、プラトンの時代の9000年前に海中に
没したとされる大陸、そこに繁栄したとされる帝国があった大陸<幻のアトランティック大陸>が、
分離没した跡の断崖であると想像してみただけで、興奮は最高潮に達した。

地球最西端モハーの断崖<Cliffs of Moher>
Sketched by Sanehisa Goto

イラスト<Cliffs of Moher>

Cliffs of Moher展望台より垂直断崖を鑑賞

Cliffs of Moher観光バスと

Cliffs of Moherの全景

イラスト <アイルランドの田舎風景>
(Trelee村)
▼ 10/5 宿泊 <The Railway Hotel> @38£
Limerick, Ireland

<The Railway Hotel>
ツアー観光バス<Cliffs of Moher & Dingle >の復路、途中で降ろしてもらい、リメリック/Limerickにある
<The Railway Hotel> に投宿する。
ここアイルランドにおいて、「ヨーロッパ周遊の旅 11000km」 の前半を終了すると
ともに、『星の巡礼 ユーラシア・アフリカ二大陸38000kmの旅』 の中間点に、よう
やく到達したことになる。
近くの中華料理店に出向いて、栄養補給と共に、<ユーラシア・アフリカ二大陸38000
kmの旅>前半終了を祝ってギネス・ビールで乾杯した。
ウラジオストックをスタートし、シベリア横断鉄道でユーラシア大陸をまたぎ、スカン
ジナビア半島を南下し、イギリスからアイルランドに至る全行程の約半分19000kmを
無事踏破できたことへの感謝と、これよりの中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、中東から
アフリカを縦断し、南アフリカのケープタウンまでの後半約19000kmの旅の安全を願っ
ての乾杯である。
これまで買いためた小さな土産類や、書き溜めたスケッチ・日記ノート類・資料などを
整理・パッキングし、日本へ返送する荷造り(船便)も終える。
■ 10月6日 リメリック/Limerick
<旅は人生の縮図>
この旅は、病で亡くなった妻との約束の旅でもある。
同行二人、それは神であり、亡き妻でもあるわけだ。
多発硬化症と言う、当時難病として治療の方法さえ確立されておらず、7年間の闘病生
活をへて、天に召された。
その間、交わした夢物語や約束事をノートに記したものである。
定年を機に<サバティカル>長期休暇をとり、実行に移した。
ネパールのヒマラヤを一緒にトレッキングすること、トルコのボスポラス海峡を船で遡
行し、アジアとヨーロッパの接点に立つこと、キリマンジャロを眺め、サイドカーで日
本全国を駈け巡ろう・・・と。
わたしにとって60才からは、人生の長期休暇<サバティカル>であった。
サバティカルである<星の巡礼>の第一歩が、この『星の巡礼 ユーラシア・アフリカ
二大陸38000kmの旅』である。 この38000kmの旅に欲張って、そのほとんどの夢を
詰め込んでみたのだ。
どうしても一か所にとどまらず、出来るだけ多くの夢を実現するために、3か月の間
に、出来るだけ多くの地を駈け巡る旅となってしまった。
昨日、日本への小包(通過地記念マグネット・書き溜めた日記や資料・お土産・写真フ
イルム他)を贈るために郵便局に行き、小雨の中、列を作ってオープンを待った。
アイルランドの農夫と言う初老の男性に傘をすすめたところ、この辺りの天気について
話を聞くことが出来た。
この辺りは(アイルランド西岸中部)、毎日のように雨が降り、雲が低く垂れこめ、ど
んよりした気候だという。 冬はマイナス15度にもなり、最悪な場合、零下35度にもな
ったことがあるそうだ。 イギリスとアイルランドは「雨の国」と言われていると笑っ
ていた。
地図で見ると、北海道よりも、はるか北に位置しており、天候不順の日が多いようであ
る。

イラスト <アイルランドの緑色ポスト>
アイルランド国旗
<ケルトの列車の旅 リメリック/Limerick ➡ ロスレアー港/Rosslare>
アイルランド列車の旅は、流浪の民ケルト人の悲哀を詠ったケルト・ミュージックを聴
く旅でもあった。
この日のために、友より贈られたケルト音楽を網羅したエンヤの曲、CDをたくさん持参した。
<Shepherd Moon・Ebuda・Angels・Evacuee・Afer Ventus・・・・・・>の曲を
聴きながら、ケルトの世界へ埋没したのである。

<アイルレイル> ARROW2820型車両
ヨーロッパの中央であるボヘミアあたりで起こったケルトは、ローマやゲルマンの台頭
により、過酷な自然環境の土地であるアイルランドへと追いやられ、北からはバイキン
グやアングロ・サクソンにも侵攻された。 近代に入ってからもアイルランドはイギリ
スの搾取に苦しみ、アイルランドを捨て、移住した新天地アメリカ大陸でも差別を受け
続けた。 近年、ジョン・F・ケネディという若き新進気鋭の大統領を生んではじめて
アメリカでのアイデンディティを勝ち取ったと云われている程である。
どれだけ厳しい自然環境でも、侵略され征服されても、世界中に移民して行っても、搾
取や差別を受けても、彼らはケルト精神とアイデンティティーを失わず、敗者という意
識を持つこともなく、持ち前の不屈さと前向きな力強さで、今日までのその文化を継承
してきた人々だと云える。
ケルトの神話や伝承では、人間が様々な動物に生まれ変わったり、神や妖精と人間が結
婚したり、魂が絶えず流動する思想が見られるという。
自然の大きな輪の中で、人や動物を含むあらゆるものの魂が絶えず流動しているという
世界の捉え方がケルトの人たちの思想の特徴であるという。
それぞれの民族は、自然環境、歴史、侵略と制服、離散と移民、抵抗と回復、屈辱と苦
難、富と成功を乗越えて文化を育み、芸術を育ててきたと云える。
ケルトもまた人類の貧しさ、いや普遍が生み出した典型的な民族の一つであるといえ
る。
列車はリメリック/Limerickを出て、アイルランド南部にある港町<ロッサレ/Rosslare
>へ向かって、ケルトの世界を駈けているのである。
果てしなく続く、丘陵の波打つ360度広がる緑のケルト草原を走り続けている、まるで
夢のようである。
祈りを誘う地平への沈みゆく太陽の厳粛さ、空から垂れ下がった雲の重圧感、すべてが
神の意志のもとにあると思うだけで、ケルトの世界に引きこまれていくのである。
<フランス高校生の生態>
リメリック/Limerickを出て、アイルランド南部にある港町<ロスレアー/Rosslare>へ
向かう列車は、修学旅行生なのか満員、フランスの高校生であふれかえっていた。
まるでケルト列車が若者たちで占拠、いや乗っ取られたような有様である。
フットボール観戦のあの騒然とした様に似ている。
若者特有の若き血潮がうねりとなって伝わってきて、わたしの中のケルト世界はぶち壊
されたが、スカウトのサインである<三指>をしてみせると、なんとほとんどの子が、
三指に応えて三本指を高く上げてくれたから驚きである。
彼らはボーイスカウトでもあったのだ。
以降は、以前と打って変わって静粛に協力してくれたものだから、またケルトの世界へ
没入することが出来た。
今夜は、明日フェリーでイギリス・ウエールズの港に渡って、ロンドンに戻り、フランスから
スイスへ向かうため、ここロスレアー港にあるロッジに泊まることにした。
列車旅でのケルトの世界の余韻を楽しむために、ロッジ近くのアイリッシュ・バーで Irish
Beer<BULMERS>を一杯飲んで、床についた。


アイリッシュ・ビール<BULMERS>
▼ 10/6 <Rosslare Port Lodge>宿泊

Rosslare Port Lodge
ロスレアー港近くのロッジに泊る。
温かい出迎えを受ける。 共同部屋(ドミトリー)では、やはり60歳代のリタイア―し
た男性と同室である。 髭に白いものが混じり、流浪の老人と言えそうだ。
こちらも同じく人生の最終章にさしかった流浪の老人である。
どことなくお互い、家族の温もりに飢えているような雰囲気を醸し出し、うら寂しさを
感じさせているのだから、人生の終着駅に近づいている仲間でもある。
ホステルの窓から眺められる向かいの一軒家のかすかに揺れる灯火のように、重荷を背
負った老人が、見知らぬ遠い地を彷徨っているような気がしたものだ。
映画のシーンのようで、この情景もまたいいものだと、おのれを慰めた。
深夜、ルーフトップの明り窓から射しこむ月の光が、アイルランド最後の夜を、さらに
哀愁に満ちた情景を醸し出していた。
この最果ての国アイルランドで、月を眺めるおのれの幸せを噛みしめた。

アイルランド緑の郵便ポスト(ロスレアー駅前)
<トイレ・シャワーの水>
ここアイルランドでは、日本とは少し異なる水に対する感覚、取扱いが見られる。
環境保護の観点からか、アイルランドの節約スピリットからか、使い放題と言っていい
日本的な水感覚とは異なるのである。
どうも水の大切さを、アイルランドの人々はよく知っているようである。
その端的な例は、トイレとシャワーにある。
そこには必ずボタンが付いているプッシュ栓である。
ワンプッシュ、3秒程すると水が止るのである。
シャワーなど出し放しに慣れている日本人にとって大変であるが、慣れれば、水の有難
さが身に沁みたものである。
しかし、風邪をひいてしまう恐れがあるので、もう少し工夫、調整してもらえたら有難
いのだが・・・
■ 10月7日 暴風雨によりフェリー欠航
ロスレアー港(Rosslare Europort/ Ireland)を、朝9時出航予定のイギリス・ウエールズ・
フィッシュガード行フェリーが、直前になって暴風雨のため出航を取りやめるという。
次便は、天候次第だが、夜10時になるという。
この長旅で初めての自由時間、スケジュールにないトレッキングが出来るチャンス
でもある。
それもアイルランドの自然に囲まれた田舎町、バックパッカーにとっては貴重な時間、
大切に使うことにした。
<アイルランド南海岸トレッキング>
まず、重たいリュックを港の送迎ターミナルの長椅子にチエーンで縛り付け、サブザッ
クにトレッキング用品だけを詰込で出かけることにした。
もちろん、所有者である自分の名前・国籍・住所・トレック中・緊急連絡先を書いたメ
モも添えた。
しかし、トレックから帰って、このリュックが忽然と消えて無くなっているという事件
が起こるとは、知る由もない。
まず、港近くにあるグロッセリー(食料品店)に立寄って食料を調達(プラム・バナナ・
トマト・ビスケット・ドライフルーツ・水・オレンジ・パン・ハム)、次に昨夜泊った
港近くのロッジで、海岸のトレッキング・マップと、トレック情報を仕入れた。
大雨対策として、持参のポンチョのほかに、ナイロン袋に頭・両腕の穴をあけて、ジャ
4ンパーの下に着こみ、雨水による低体温を防ぐことにした。
トレッキングシューズも、靴下の上からナイロン袋をかぶせて履き、雨に備えた。
約6時間の<アイルランド・サウスコースト・トレッキング>を楽しむことにした。
崖の上にトレッキング・コースがあり、色とりどりの花や、ブルべリーの花が一杯咲い
ていた。
あいにく海は荒れ、強風、大雨の中のトレックである。 アイルランドはどこでもそう
だが、海岸線いっぱいまで牧草が生え、牛が放し飼いされている。
トレッカーが通ると、牛達が二列に並んで、こちらをじっと観察する。
あたかも <人間って面白いね。 こんな雨の中、音楽を聴きながら歩くなんて、
何してるんだろうね>と、お互い顔を突き合わせて、草を食むのも忘れてあきれ顔である。
西端モハーの断崖<Cliffs of Moher>ほどの絶壁断崖ではなく、ゆるやかな断崖で、
その淵まで牧草が生える大草原である。
雨の中、ただ一人アイルランドの見知らぬ海岸を、ケルト・ミュージック<エンヤ>を
聴きながらトレックするという贅沢を味わった。
崖っぷちには、牛達が崖から落ちて海で溺死しないように太い針金が張ってあるのだが、
これには高圧の電流が流れているのである。
最初、針金をまたぐとき少し触れたのであろう、頭と心臓にショックが走った。
なんと、股の下が雨でぬれていて通電したのである。
以降は、必ず高圧電流線をまたぐ柵を使ってトレックを続けた。
カモメたちは風に乗ってアップ & ダウンを繰り返しながら、こちらと並んで飛び続
け、フレンドリーである。
暴風雨下の波は、一番乗りを競って崖下に激突し、波しぶきを吹き上げ、シャワーの洗
礼である。
強風は、これでもかと体当たり、よろよろしながらの前進。
アイルランドでのトレッキングも、ヒマラヤのトレックと同じく記憶に残りそうである。

暴風雨のなか高圧電線をまたぐ柵を越える

緩やかな崖になっている南アイルランドの海岸線をトレック中

ロスレアーの港町にもどる
<リュックが消える>
トレックから帰ってみると、フェリー乗り場の長椅子に自転車用チエーンで長椅子に固
定しておいたリュック(バックパック)が、失せていた。
よく見ると、鉄バサミで切りちぎられたチエーンが長椅子に残り、リュックが持ち去ら
れているではないか。 もし窃盗であれば、取り返すことは至難の業であろうし、最終的
には目的地である南アフリカのケープタウン行をあきらめ、残念だが帰国しかない。
さっそくターミナルの売店に急ぎ、尋ねて見た
店員によると、パトカーと消防車が駆け付け、不審物としてリュックをチエーンから切
り離して、持ち去ったという。
持ち去った先は、すぐに判明した。 親切な店員は、ポリスに電話してくれたのである。
説明によると、フェリーターミナルの警備員(一か月前にアメリカで起こった9:11テロ
事件<米国同時多発テロ>を警戒中)から不審物があるとの連絡を受け、その関連性を
調べるため警察に押収されていた。
9:11テロでは、アフガニスタンのイスラム原理主義タリバンによるアメリカ・ニューヨ
ークの世界貿易センターへの突っ込み、また二機目のワシントンDCにあるペンタゴンへの
突入未遂、三機目の乗っ取り自爆と言う同時多発奇襲テロにより、多くの犠牲者を
出していた。
世界中が厳戒態勢を敷いてお折り、この旅でも9:11事件当日は、丁度ウラジオストクか
らシベリア横断鉄道でモスクワに向かっていた途上、新聞で知って驚くと共に、これから
の行き先々での国境や、交通機関での検問の強化は覚悟したものである。
その後、ユーロスター乗車時の厳しい荷物チェックや、尋問に辟易していた。
とくに、バックパッカーの荷物や行先に、鋭い目が向けられていた。
リュックに爆弾が仕掛けられてれているのではないかと、爆弾処理班が近くの広場の真
中にリュックを置き、取り囲みながら観察し、リュックを爆破処理する準備を進めてい
た。
何とか間に合い、説明を尽くし、リュックを置いてトレックに行っていたことを説明
し、詫びを入れ、リュック返却を懇願した。
雨でずぶ濡れの東洋人がこのような田舎町で何をしているのかとのいぶかしさを隠すこ
ともなく、異様な眼差しでにらみつけて居る。
もちろん身分証明と、リュック内容について厳しい検査と尋問を受けた。
特にハサミ・サバイバル用ジャックナイフ・フォーク・ライター・マッチに注目が集ま
った。
最終的に、テロリストではなく一般のバックパッカーであることが認められ、リュック
と共に解放されたが、携帯物は身から離すなとのお叱りを受け、放免された。
フェリー・ターミナルに戻ってみると、暴風雨のため夜10時に延期されたフェリーに乗
る客と、同じ時刻にフランス・ノルマンディー方面に向かうフェリーの乗客で混雑して
いた。 特に列車で一緒だった100人ほどのフランスからの修学旅行中の高校生が目立
って賑やかであった。
若者たちと交流していると、英国ウエールズ行のフェリーは、悪天候を理由に明朝9時
に出港するとの再順延のアナウンスが流れ、乗船客からあきらめのため息とブーイング
が起こった。
こちらは、丸一日スケジュールが無くなったことになり、先を急ぐためにはイギリス経
由ではなく、直接ヨーロッパへ向かう事を決断した。
さっそく、夜10時に出港するフランス・シエリーブル/ Cherburg行きフェリーの乗船手
続きを済ませた。
長旅をしていると、思いもよらない色々なことが起こるものである。
臨機応変に対処し、スケジュールを修正する必要がある。
▼ 10/7 <Irish Ferries / フェリー アイリッシュ> 船中泊
(フランス・Cherburg / シェリブール行フェリーに変更)

Irish Ferries / フェリー アイリッシュ

Irish Ferries / フェリー アイリッシュ 航路図
<アイルランド/Rosslare ➡ フランス/Cherbourg>
■ 10月8日 <Irish Ferries / フェリー アイリッシュ>
<アイルランド/ロスレアー港22:00出航 ➡18:00着予定 フランス/シェリブール港>
(約20時間の船旅を楽しむ)
暴風雨の中での出航、2時間遅れの真夜中0:00の出航となった。
10月8日の午後8時ごろ、ノルマンディー近くのフランス/シェリブールに入港する予定
だという。
ノルマンディーは、第2次世界大戦におけるドイツの敗北を決定づけた連合軍最大の反
攻<ノルマンディー上陸作戦>が行われたところである。
少年のとき観たニュース映画<ノルマンディー上陸大作戦>は、日本敗北の前哨戦とな
った連合軍の猛反撃による同盟国ドイツの敗北としてとらえたものである。
そのノルマンディーに、これから上陸するのだと歴史的証人であるかのような興奮を覚
えた。

ノルマンディー(フランス)上陸前の夕陽を眺める

挿絵 <フェリー・アイルランド号 航路図>
とにかく、アイルランド脱出作戦にようやく成功した。
旅は、天候次第であることが良く分かるのである。 天候は、旅のすべてを左右すること
を肝に銘じた。 特に一人旅であるバックパッカーは、天の行いにただただ従うことが
精神衛生上良いのである。 問題あればいつかは解決し、道が拓けると思えば、我慢も
また旅上手の一手である。
しかし、先を急ぐバックパッカーにとって2日間のロスは、ただただ我慢し、辛抱の時
間であった。
フランスの修学旅行生とも仲良くなり、学生たちの希望で、数名の子の名前を漢字に書
き替えてプレゼントしたり、スケッチに彩色していると、仲良くなった生徒たちが、ス
ケッチにサインをしてくれたものだ。

アイルランド・ロスレアーの街並み
With signature of students
Sketched by Sanehisa Goto
学生たちと交流していると、日本語で語りかけてくる青年 金子君(埼玉出身・哲学専
攻・哲学者バッハ研究・大学2年)がいた。
アイルランド・ゴールウエイでの 6か月 の語学留学を終え、ヨーロッパ観光の後、帰国
するという。
この時の日本語のなんと心地よかったことと、日本語が遠くの言葉になっていることに
気づいた。
ロシア・ウラジオストクをでて、ここまでの約2か月の間、日本語を使っていなかった
からである。
かえって、なぜ地の果てのローカルなフェリーに日本の青年が乗船しているのかと不思
議に思ったものである。
旅のスケジュールが、悪天候のため変更せざるをえなくなったので、修正が必要であっ
た。
さっそく金子君からThomas Cockの時間表を借り、スケジュールを短縮し、向かうスイ
スのジュネーブまでの路線を確定し、時間表を書き写した。
フェリーは、いまだ暴雨風の余波で、船体を上下に揺らし、左右に傾き、船旅に慣れな
い彼はすでに船酔い気味である。
船酔いの苦しさは、体験したものでないとわからないと思うが、こちらは小学校4年生
のとき、引揚船で朝鮮半島の釜山から門司へ引揚げてきたときに、生死をさまよう船酔
いの洗礼を受けたことがある。
その後、世界一周を貨客船や、客船で数度経験するほどに船旅を愛するようになって
いたのでケロッとしていた。
船酔いの苦しみは、船が大波の波間に沈み、浮き上がるその振幅が大きければ多き程、
苦しみが増すのである。 引揚時の対馬海峡での経験では、大波は上下に15~20m
程であったと記憶する。
船が波間の底に沈んだ時は、波の先はビルディングの7階ぐらいの高さであり、まるで
地獄の底に吸い込まれたような錯覚になり、吐き気と共に胃が口から飛び出すような感
覚に襲われる。
フェリー・アイルランド号は揺れ続け、あちこちで物が落ちる音がしている。
不規則に船が揺れて、ズーンと底に引きずり込まれるようになる。
修学旅行生も静まり返り、嘔吐にせき込む音が激しくなってきた。
彼も船酔い気味で、口に手を当てて虚ろである。
今夜は眠れそうもなさそうである。

フランスの修学旅行生たち
フェリー・アイルランド号にて
Sketched by Sanehisa Goto

フランスの修学旅行生たち(フェリー・アイルランド号にて)
夜を徹して揺れまくった船体も落ちつき、カフェテリアで朝食をとっていると、荒波と
ぶつかったのだろうか、椅子と共に吹っ飛んだ。
あっちこっちで皿が割れる音がして、騒然となった。
朝食のメニューも限定するとのアナウンスが流れた。
この揺れでは、サニーサイドアップの卵焼きも難しいのであろう。
ヨーグルトと、パン&オレンジジュース、コーヒーで朝食を切り上げた。
《わが連合艦隊は、現在、英国南岸を東進中、ノルマンディー/シェリブールに
22:00に上陸せんとする。全員上陸準備をして甲板に集合せよ》
とアナウンスが流れたように聴こえた。
荒天で、眠れない夜を過ごした乗船客が、船倉の客室から甲板にでて、雲間から顔を出
す太陽に向かって両手をひろげ、盛んに深呼吸をしている。
なかに金子君も太陽を拝んでいた。 転覆の危機を脱した極度の安堵が、乗船客を感謝
の気持ちにさせているのであろう。 この時の太陽は、救いの女神に見えた。
客室のある船倉は、一枚の鉄板で天国と地獄を分けている空間である。
荒波に軋む金属音は、乗船客の極度の恐怖をいやおうなしに高め、祈りへと駆り立てる
のである。
ひとはみな、トルストイ著<光りのあるうちに、光の中を歩め>の豪商ユリウスのよう
に、何度か宗教(キリスト教)の世界に走ろうと志しながらも、そのたびに俗世間に舞
いもどるが、しかし、長い魂の彷徨の末についに神の道に入る。
船旅とは、昔から一大決心と、今生の別れが求められ、テープを投げ合って別れたもの
である。
ふと、この船旅で青年時代を想いだしていた。
大学を出て、電機会社に就職したのが東京オリンピック(1964)の年の春であった。
青葉城跡近くの仙台支店に配属となった。
素晴らしい先輩や同輩に恵まれながらも、職を辞し、かねて希望していたブラジルへの
スカウト移民に選抜され、ブラジル・サンパウロに向かうこととなった。
ドラム缶に荷物を詰め、移民船「さくら丸」の船倉で、荒波に揺られての48日間の船旅
であった。
それ以来、船旅は、わが人生の一部となったのである。
ヨーロッパの旅前半の締めくくりとして、日本の青年に出会い、船酔いと言う洗礼を受
けながら、ノルマンディー上陸作戦を敢行することとなった。
大雨の中、フェリー・アイルランド号は、夜10時、フランス・ノルマンディー海岸のシェリブー
ル / Cherburg港に接岸。 連合軍とドイツ軍の大激戦地ノルマンディーへ上陸、ナバロ
ンの要塞を想像し、興奮も最高潮に達した。
フェリーで出会った青年バックパッカー2人と金子君、4人で近くの列車駅目指して歩き
だした。 途中で、近くのユースホステルを知っているというカナダのバックパッカ
ー・サンドラ嬢が加わり、深夜でもあり、YHで一泊することになった。
▼ 10/8 <シェリブール・ユースホステル>泊 (朝食付き 110F)

ここフランスの港町シェリブールで「星の巡礼・ヨーロッパ周遊の旅 1100km」の前半
を終え、いよいよ後半、ヨーロッパ全土を<ユーレイル・パス>を使って列車で駈け廻り、中
東にあるイスラエルに立寄り、エジプトよりアフリカを縦断し、アフリカ最南端にある
喜望峰に向かいたい。

今回の90日間にわたる《ユーラシア・アフリカ 2大陸踏破 38000km》の旅姿を
イラストで紹介

バックパック(携行品)の中身

90日間《ユーラシア・アフリカ 2大陸踏破 38000km》おおよそのルート図
『星の巡礼 ヨーロッパ周遊の旅 11000km』
Ⅰ ヨーロッパ前半
完
------------------------------------------------------------
Ⅱ ヨーロッパ後半
に続く
現在作業中
------------------------------------------------------------------------------------------------
<関連ブログ>
shiganosato-goto.hatenablog.com
shiganosato-goto.hatenablog.com